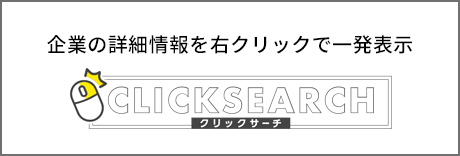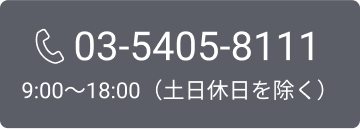【新卒者の悩み解決!】テレアポ営業でアポ率/受注率を上げる10のコツを紹介

感染症の流行以降、企業の営業/マーケティング活動はますます難しくなっています。特にtoB業界では展示会やセミナーの休止・規模縮小が相次ぎ、多くの企業がリード獲得のチャネルを失ってしまいました。そんな時にリード獲得に有効なのがテレアポ(電話営業) です。しかし、既存顧客に対する架電ならまだしも、新規顧客への架電で、アポイントメントや成約に繋げるのは難しい現状があります。
弊社でもリード獲得手段としてテレアポを活用していますが、始めた当初はなかなか結果が出ず、100件かけても1件も取れなかったということはザラにありました。しかし、テレアポを繰り返すうち徐々にノウハウが蓄積され、一定の成果が上がるようになっていきました。そこで、弊社が数千件ものテレアポで得たアポ率/受注率UPに繋がるコツを10個に厳選してご紹介いたします。
本記事は、「新卒でテレアポ営業をしているけど、うまくいかない」「成果が出るコツが知りたい」という方向けに書かれています。toB向けのコツが中心ですが、テレアポを始めようと考えている全ての方にとって、参考になる内容だと思います。是非ご覧ください。
テレアポ営業が必要な理由

テレアポ営業のコツを伝える前に、「今どきテレアポなんて効率も悪いし時代遅れでは?」「テレアポなんて本当に必要?」という風に考えてしまい、中々モチベーションが上がらない方もいるのではないでしょうか?
確かにインターネットが普及した今では、わざわざ売り込まなくてもインターネットを使って自分で情報収集を行えますし、リスティング広告などのWeb広告を使えばある程度の集客が見込めます。
しかし、顧客のインターネット検索に自社のサービスを引っかけるためには、地道なSEO対策(検索順位をUPするるための取り組み)が必要となりますし、有料のリスティング広告などで一定の効果を見込むには月に数十万~数百万の広告費がかかってしまいます。
特に起業して間もない会社や中小企業の場合は、SEO対策やWeb広告に関する充分なノウハウや費用を持っていないことが多く、潤沢な予算や豊富な人材を持つ大企業と同じフィールドで渡り合わなくてなりません。
一方で、テレアポ営業には有料広告ほどの費用もかからず、コミュニケーション能力さえあれば、専門的なノウハウも必要ありません。以上のことから、インターネットが普及した現在でも、テレアポ営業は新規顧客の獲得のために必要な仕事なのです。
テレアポ営業で成果が出る10のコツ

この章からは、テレアポ営業で成果が出るコツとして、事前準備編と実践編の大きく二つに分けて計10個を紹介していきます。
- 事前準備編
- ・コツ①最適なトークスクリプトを作成する
- ・コツ②PDCAサイクルを回す
- ・コツ③ツールの活用をする
- ・コツ④質の高い営業リストを用意する
- ・コツ⑤架電する時間帯を絞る
- 実践編
- ・コツ⑥話すトーンは低く、ペースはゆっくりに
- ・コツ⑦担当者の名前を聞き出す
- ・コツ⑧クローズドクエスチョンを活用する
- ・コツ⑨冒頭のトークを工夫する
- ・コツ⑩無理な売り込みをしない
新卒の方に限らず、「初めてテレアポをするけど、やり方が分からない」という方は、これから紹介するコツを意識するだけで、テレアポ営業の成功率が格段に上がると思います。
コツ①最適なトークスクリプトを作成する

トークスクリプトとは、テレアポに使用する台本のことです。このスクリプトの優劣が、テレアポの成否に繋がると言って間違いないでしょう。最適なトークスクリプトを作成するうえで、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
①トークスクリプトはできる限り詳細に
スクリプトは、「そのまま話せば問題ない」というレベルまで詳細に作るといいでしょう。また、話す内容を箇条書きや書き言葉にするのではなく「〜ですよね」とか「そうなんですね」など、細かな語尾やニュアンスも含めてスクリプトに含めます。そうすることでスクリプトを読むだけで自然と会話ができるようになり、架電する営業マンによるレベル差を埋めることができます。
もしテレアポに慣れている先輩営業マンが社内にいるのなら、一度その人にトークスクリプトの手本を作成してもらうのも手です。そして大まかなトークスクリプトができたら実際に架電してみて、徐々にブラッシュアップしていけば効率的にトークスクリプトの質を上げることでができるでしょう。
②営業相手の属性に合わせてスクリプトを調整する
すべての相手に対応できる汎用的なトークは、心に残りにくく成果に繋がりません。営業相手の属性(業種・企業規模など)を把握した上で、ターゲットに応じて効果的なスクリプトを作りましょう。例えば、営業相手からしてみれば、口頭でサービスの説明を長々とされてもピンときません。営業相手の属性と似通った導入事例などが自社にないか事前にチェックしておき、スクリプトに組み込むことで、相手も自分ごととして捉えやすく、話を聞いてくれるきっかけとなるでしょう。
③断り文句に対する切り返しを用意しておく
テレアポを受ける側は、常に電話を切るタイミングを探っています。そういう時に出るのが断り文句です。
良くある断り文句を例に挙げると、以下のようなものがあります。
- 「価格が高い」
- 「もう似たサービス(競合)を導入している」
などです。
それらの断り文句に対して「このプランだと安く済みますよ」「そのサービスにはこういう欠点がありますよ」と事前にいくつか想定して用意しておくことで、いざという時に冷静に切り返すことができます。
また、初めて言われた断り文句などは常にデータとして溜めておき、スクリプトの改善に役立てることも忘れないようにしましょう。
コツ②PDCAサイクルを回す
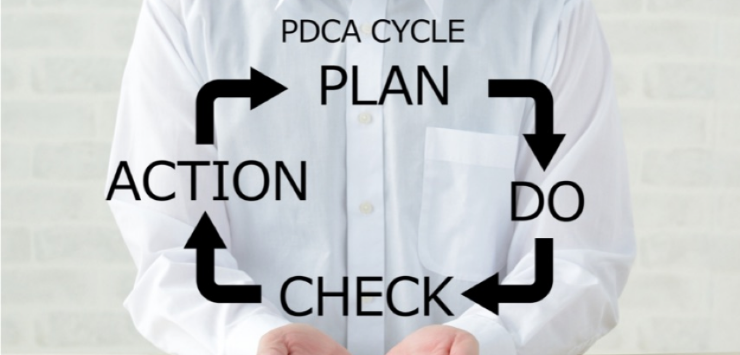
テレアポに限らずはじめての取り組みはなかなかうまくいかないものです。トライ&エラーを繰り返し改善ポイントを見つけ、ノウハウを蓄積していきましょう。具体的には下記のようなプロセスで実行するといいでしょう。
Plan 計画
何日までに、何コールかけて、何件担当者に繋がり、何件アポイントメントを取るのか、無理のない範囲で目標値を事前に設定します。また、重要なのは目標値だけでなく、営業同士の情報共有やフィードバックのやり方などもこの段階で固めておきましょう。
Do 実行
「Plan」で決めたことを着々と実行していくフェーズです。この段階で得た顧客の情報などは逐一記録して、しっかりとデータベース化していきましょう。
Check 評価
目標値に対して、実際どうだったのかを定量的に評価していきます。この場合大切なのは数字を達成したかどうかではありません。なぜ達成できたorできなかったのかという原因を見つけることに注力しましょう。
Action 改善
うまくいかなかった原因を改善し、次の目標を立てるフェーズです。
例えば下記のような改善例が考えられます。
- ・トークスクリプトの改善(無駄なトークを減らすなど)
- ・ITツールなどを使って、情報共有を効率化させる
- ・営業リストの更新など
コツ③ツールの活用をする

テレアポでは、膨大な数の営業リストの作成や修正、さらにテレアポで得た情報を共有していくという作業が必須です。そういった作業は時間がかかるうえ、テレアポの効率を低下させ、コール数やアポ数が伸び悩む原因となります。そこでおすすめなのがITツールの活用です。
以下ではテレアポをさらに効率化するITツールを3つご紹介します。
自社のテレアポ業務に活用できるか確認してみてください。
SFA
SFAとは営業マンの日々の営業活動の自動化や営業活動により得られた情報全般をデータ化して、蓄積・分析が行えるシステムです。特にテレアポにおいては『Excel』や『GoogleSheets』などのツールを活用する場合が多いですが、情報の共有性や蓄積という面においてはSFAの方が優れています。また、テレアポで獲得したメールアドレスなどに自動でメール配信で追客できるため、テレアポの一層の効率化が期待できます。
営業リスト作成ツール
その名の通り、テレアポに利用する営業リストを簡単に作成できるツールです。一般的に新規顧客への営業リストを作る際、ポータルサイトや会社HPなどから手作業で地道に収集するしかなく、これには相当な労力がかかります。そこで営業リスト作成ツールを利用すると数十万件ものリストから業種別、資本区分など様々な条件に従ってリスト作成が可能な為、リストに費やす労力の削減や、アポ率/成約率に直結するリストの質の改善を行えるのです。
CTI
CTIとは、電話とITツールを連動させることで、テレアポやカスタマーサポートといった電話業務を効率化するツールです。CTIを活用することで、従来なら電話機で操作するべき電話の発信や受信などもパソコンの画面上のボタンをクリックするだけで可能となり、顧客情報などもシステム上に蓄積されるため、架電・情報共有などの面でより一層の効率化が期待できます。
コツ④質の高い営業リストを用意する

どんなに素晴らしい営業マンでも、架電のための営業リストの質が悪ければ成果を出すことは困難です。リストの質を高めるためには、以下の2つのポイントを押さえましょう。
- ・情報量の多さ
- ・情報の鮮度
情報量の多さ
営業リストには社名や連絡先(電話番号・アドレス)だけでは不十分です。下記のような情報があると架電時のトークがやりやすくなります。
- ・部署直通の電話番号
- ・ホームページのURL
- ・業種/業態
- ・企業情報(設立日、資本金、売上、社員数、拠点など)
また、テレアポ時に手に入れた情報は、必ず営業リストに紐づけて忘れずに記録するように徹底しましょう。
テレアポをかけるほど、リストの質は上がっていき、会社の財産ともいうべきリストになっていきます。
情報の鮮度
たとえ、圧倒的な情報量を持つリストでも、記載されている情報が古かったり間違っていたりすると、架電時に調べなおす必要があり、効率の悪化に繋がります。営業リストは、信頼できる情報源を活用し正しい情報で作成することはもちろん、定期的な更新や見直しが必須となります。
コツ⑤架電する時間帯を絞る

テレアポといえば、一日中受話器を片手に架電し続けるイメージがあるかもしれませんが、下記3つの理由から推奨できません。
- ・集中力が続かず架電速度やテレアポの質が落ちる。
- ・フィードバックや情報共有が後回しになる。
- ・始業後や終業間近の時間帯は顧客に対応され辛い
そのため、時間帯をある程度絞り、集中して架電を行うことをおすすめします。
成果が上がりやすくなる傾向があります。
おすすめの時間帯
始業から1~2時間後、ランチタイムから1~2時間後の時間帯は比較的手が空いているため、次の時間帯に架電するのがおすすめです。
- ・10時~11時半
- ・14時~16時半
このスケジュールで架電すると、午前中に担当者不在で繋がらなかった顧客に対しても、温度感が下がらないうちにアプローチできる上、フィードバックや情報共有の時間もしっかり確保できます。
コツ⑥話すトーンは低く、ペースはゆっくりに

テレアポにおいて重要なのが、声質や声のトーンです。一般的に、テレアポはハキハキとした明るいトーンで喋るという印象があるかもしれませんが、いかにも営業電話という雰囲気は、相手に警戒心を抱かせてしまいます。
また、テレアポは相手の時間を奪って自社の商品を売り込んでいるという大前提があることを忘れてはいけません。すこし落ち着いたトーンで、ゆっくりと話すことで相手によい印象を与えることができますし、担当者へ繋がる可能性も高くなります。
では具体的にどう喋るかというと、通常時の80~90%ぐらいを意識して、トーンやペースを調整すると良いでしょう。
効率のいい練習方法
口で言うのは簡単ですが、いきなりそんな調節ができる人はなかなかいません。下記のような練習方法で身に着けていきましょう。
- ①トークスクリプトを音読し、ボイスレコーダーで録音
- ②同僚や先輩をお客様に見立てて電話をかける(営業ロープレ)
特に電話は口頭で話すよりも聞き取り辛く、聞く側の印象もかなり変わってしまいます。②の練習は必ずしておき、他の社員からのフィードバックをもらいつつ練習を重ねていきましょう。
コツ⑦担当者の名前を聞き出す

テレアポで最大の障壁となるのが、受付です。
基本的にテレアポをしても、最初に営業をかけるべき担当者(キーマン)に繋がることはほとんどありません。
特に新規で電話をかける場合は、当然担当者の名前もわからない為、「社長様」「担当者様」などと表現するしかなく、一気に営業電話の雰囲気が出てしまいます。
そのため、テレアポの第一目標として担当者の名前を聞き出すことをまず意識すると良いでしょう。
例えば、受付の方に「担当者は不在です」と断られた場合、担当者の名前を聞き出し、時間を改めてかけなおすだけで、担当者に繋がる確率が格段に上がります。
もちろん、基本的に名前を教えてくれないことの方が多いので、受付の方から担当者名を聞き出すために利用できるテクニックをいくつか紹介します。
担当者の名前を聞き出すテクニック
■「担当者は不在です」と言われた場合
「次はどなた様宛にお電話すればよろしいでしょうか?」と切り返しましょう。ポイントは「担当者様のお名前を聞かせていただけないでしょうか?」という聞き方をしないことです。
特に電話が切れる直前に、「最後に一つだけお聞きしたいんですけど…」と切り出して、上の文言を言うとより効果的です。その際は、相手の「はい」「ええ」などの返答を待つといいでしょう。人間には、一度「yes」といった質問に対して、心理的に断り辛くなるという傾向があるからです。
コツ⑧クローズドクエスチョンを活用する

クローズド・クエスチョンとは、相手が「Yes or No 」のような二者択一で答えられるよう、回答範囲を限定した質問の仕方です。例えば前項の担当者の名前を聞き出すテクニックで紹介した「次はどなた様にお電話すればよいですか?」という聞き方もクローズドクエスチョンを活用した手法です。
担当者の名前を言うことがさも当然かのような聞き方をすることで、相手の回答範囲が限定され、こちらが望む回答を引き出しやすくなるのです。
クローズド・クエスチョンは、相手の回答を引き出したい時に有効ですが、誘導尋問のようで不快に思う方もいますので、押しつけがましくなりすぎないように、多用は厳禁です。また、「不要であれば遠慮なくおっしゃって下さい」や「御社の状況はいかがでしょうか」といった相手に委ねた丁寧なヒアリングも忘れないようにしてください。
次にテレアポで使えるクローズドクエスチョンの一例を紹介します。
テレアポで使えるクローズドクエスチョン
■担当者にアポの日程調整をお願いする時
・直近で都合のいい日はございますか?
この聞き方は相手に考えさせる余裕を与え「ちょっと忙しいんだよね」「今繁忙期なので…」という風に断りやすくなってしまいます。
そこで、クローズドクエスチョンを活用すると以下のようになります。
・来週の〇日と〇日でしたら、どちらが時間を取りやすいでしょうか?
このように具体的な選択肢を提示し、回答範囲を絞ることで日程に関する回答を引き出しやすくなるのです。
コツ⑨冒頭のトークを工夫する

テレアポは最初の30秒がとても重要です。この冒頭のトークで自分に関係ない電話や担当者に繋ぐ必要のない電話だと判断されてしまうと、即座に相手は「どうやって断ろうか」というモードに入ってしまい、話を聞いてくれる態勢ではなくなります。
そこで以下のポイントを押さえて話すといいでしょう。
- ・営業であることを無理に隠さない
- ・要件を最初に伝える
- ・自社サービスの詳細な説明はしない
- ・相手のメリットだけを簡潔に説明する
ポイントは率直に、短く、要点を押さえるということです。営業の雰囲気を隠そうと濁しても、相手には必ず悟られるので無理に隠すのは禁物です。かといって、長い営業トークを捲し立てても。必死に売り込みたい感じが伝わり、相手の頭にも入り辛くなります。
また切り出し方として、「今、お時間は大丈夫でしょうか」「お忙しいでしょうか」という言葉も使わないようにしましょう。相手に配慮したトークではありますが、断りやすい状況を作り出してしまいます。
コツ⑩無理な売り込みをしない

新規顧客へのテレアポは断られるのが前提です。そんな中で大切なのは、1回の架電に時間を割かず、できる限りコール数を稼ぐことです。見込みがなさそうだと判断した場合は、丁寧にお礼を言って会話を終了させ、次の企業へ架電する方が成果は上がりやすくなります。
また、テレアポを受ける立場からしても、しつこく食らいついてくる営業電話は迷惑行為以外の何物でもありません。
テレアポによって相手の時間をいただいているという自覚を持ち、興味を持たれなかった場合はおとなしく引く。
そういった心構えは営業する側・される側の両方にメリットがあると言えるでしょう。
断られたときの注意点
さて、無理に売り込むのは良くないという話をした後に手の平をかえすようですが、すべての断り文句に素直に従っていれば、一向に成果は上がりません。相手の態度やヒアリングした情報から判断しつつ、以下の点に注意しましょう。
相手の態度はどうか
話を聞く気のない人は態度でわかります。逆に少し悩んでいるような人の断り文句に対して、「どういった理由でしょうか?」と聞くと、会話がつながる可能性があります
次に繋げられるか
例えば、「最近他のサービスを導入して」「今は時期的に…」という断られ方なら、サービス資料だけでも送らせてもらい、期間を空けてから架電すると、今度はすんなりとアポが取れてしまうことも良くあります。企業のサービス検討時期というのは波があるので、再架電の際は3ヶ月ほど期間を空けて連絡しましょう。
テレアポ営業には『B-suite』

さて、最後にオススメしたいのが営業リスト作成サービス『Papattoクラウド』です。
『Papattoクラウド』は約60万社の会社HPから収集した詳細な企業データから、貴社の受注につながる最適な企業リストを即座に生成できます。基本的な住所、電話番号、業種などはもちろん部署ごとの情報や「展示会出展」「海外進出」といった76種の【活動タグ】、「テレワーク」「IoT」といった135種の【分野タグ】により、さらに的確なターゲティングが可能になっており、質の高い営業リストの作成に貢献します。
特に部署直通の電話番号がリストに記載されていることで、担当者に電話が繋がる可能性が高く、通常の代表電話番号に架電するよりも遥かにアポ率が高くなる傾向にあります。また、企業情報の更新は2か月ごとに自動で行なわれるため常に最新のデータが利用できる上、利用料金も1件5円と業界最安クラスの料金でご利用いただけます。もし、ご興味があれば下記から詳細をご確認ください。
まとめ

最後に、今回紹介したテレアポ営業のコツ10個をもう一度おさらいしておきましょう。
- ・コツ①最適なトークスクリプトを作成する
- ・コツ②PDCAサイクルを回す
- ・コツ③ツールの活用をする
- ・コツ④質の高い営業リストを用意する
- ・コツ⑤架電する時間帯を絞る
- ・コツ⑥話すトーンは低く、ペースはゆっくりに
- ・コツ⑦担当者の名前を聞き出す
- ・コツ⑧クローズドクエスチョンを活用する
- ・コツ⑨冒頭のトークを工夫する
- ・コツ⑩無理な売り込みをしない
また、テレアポ営業は、新規顧客の獲得のために重要な仕事だということをしっかりと覚えておいてください。
この記事を読んだあなたが、10つのコツを活用して、テレアポ営業で成果が出ることを心から祈っています。