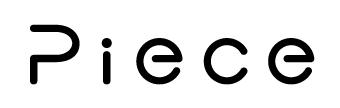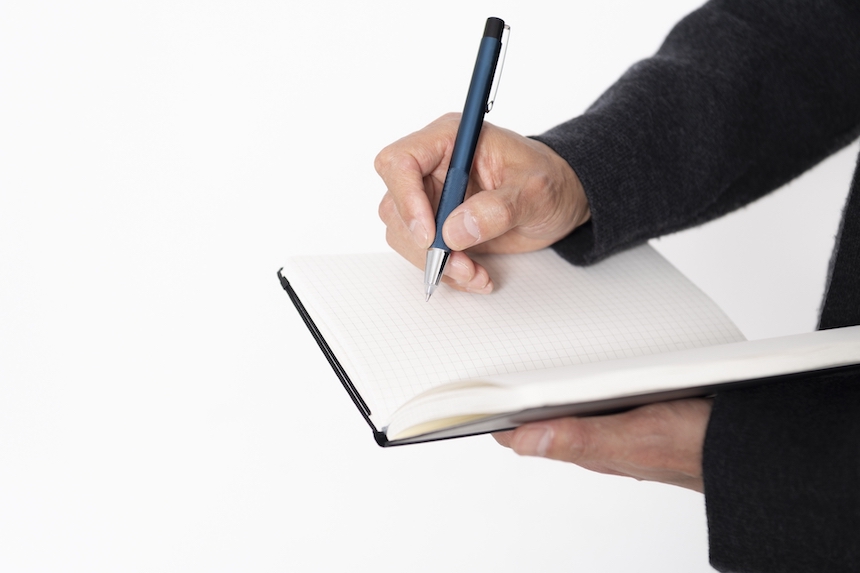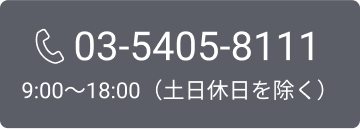オンライン商談のデメリットと対策方法【トラブルを避けよう】

「オンライン商談を取り入れるか迷っている」「デメリットを知った上で判断したい」と考えている人は多いでしょう。
リモート化が進んでいる影響で、営業もオンライン商談で訪問不要にする会社が増えています。
しかし、オンライン商談を取り入れると、営業の仕方そのものが大きく変化するため、気軽に踏み出すのは難しいかもしれません。
そこでこの記事では、オンライン商談のデメリットと対策方法を紹介していきます。
導入前にデメリットを知ることで、導入すべきかどうかわかりますし、導入後にどう対策したらよいかが理解できるでしょう。
また、この記事ではデメリットをより理解しやすくするため、会社にとってのデメリットと営業マンにとってのデメリットに分けて紹介していきます。
この記事を参考にしながら、オンライン商談を導入すべきかどうか、判断してみてください。
【この記事の内容】
【会社】オンライン商談のデメリット3つと対策法
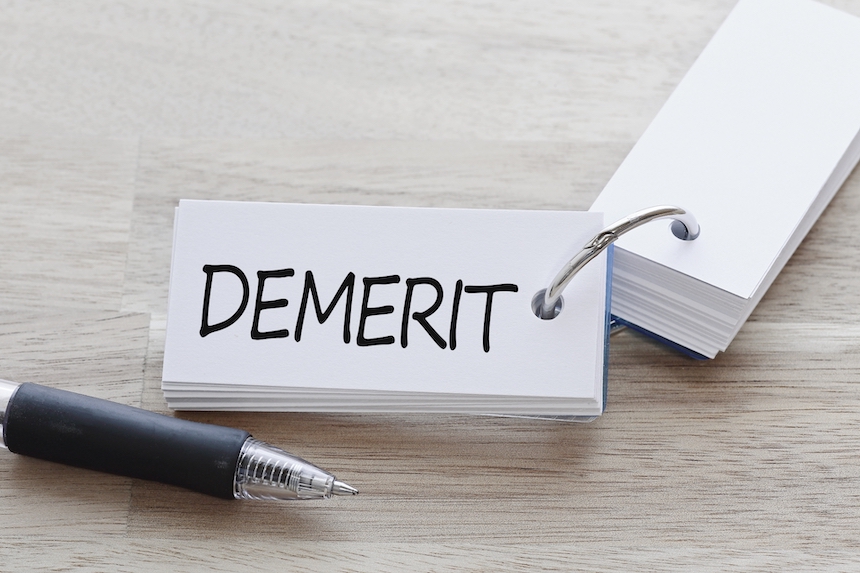
感染症対策やコスト削減に役立つオンライン商談ですが、デメリットもあります。
デメリットを知っておかないと、導入してから後悔する可能性があるので、ここで確認しておきましょう。
まずは、会社にとってのデメリット3つを紹介していきます。
- 社内に浸透しにくい
- 顧客からの理解が必要
- 通信環境の整備が必要
次章以降で以上3つをさらに詳しく紹介します。
対策方法も併せて紹介しているので、「導入するとしたらどうしたらよいのか?」を考えながら読んでみてください。
【会社】オンライン商談のデメリット①社内に浸透しにくい

オンライン商談を取り入れても、営業マンが受け入れてくれなければ意味がありません。
若い世代は、新しいものや自由な働き方に抵抗が少ない傾向があり、受け入れてくれる可能性が高いでしょう。
しかし、役職についている世代などは、オンライン商談を受け入れるのが難しいケースもあります。
デジタル機器に苦手意識があったり、「対面こそ正義!」と対面営業に強い熱意を持っていたりする場合があるからです。
対策としては、社内でオンライン商談ツールを導入する目的を共有したり、使い方の指導などをしたりするとよいでしょう。
急に取り入れると抵抗感が強まりますので、前々から告知しておき、十分に理解が得られてから導入しましょう。
ツールによっては、ツールが社内に定着するよう、コンサルタントが丁寧にサポートしてくれる場合もあります。
社内に定着するかどうか不安な場合には、サポート体制が整っているツールを選ぶとよいでしょう。
【会社】オンライン商談のデメリット②顧客からの理解が必要

オンライン商談を導入する場合には、社内だけでなく顧客からの理解も必要です。
新規客であれば、「この会社はオンラインなのね」とあまり抵抗なく受け入れてもらえる可能性が高いです。
しかし、昔からつながりのある顧客の場合、急にオンライン化すると「前の方が良かった」などと不満が出るかもしれません。
オンライン商談に切り替えるときには、事前に挨拶に行き、オンライン化することを伝えるようにしましょう。
可能であれば、ツールの操作方法なども伝え、問題なく利用できるようサポートするとよいでしょう。
また、デジタル機器やネットに慣れていない人でも、簡単に利用できるツールを選ぶことも重要です。
操作方法が簡単であればあるほど、顧客が了承してくれる可能性が高まるからです。
デジタル機器に慣れていない人からすると、アプリのインストールだけでも「アプリってなんだ?」「インストール?」などと戸惑います。
顧客側に面倒な手続きがいらないツールを選ぶとよいでしょう。
【会社】オンライン商談のデメリット③通信環境の整備が必要

オンライン商談では映像をリアルタイムで配信するため、安定した通信環境が必要です。
通信環境が安定していないと、商談中に音声や映像が乱れ、思うように商談を進められません。
今まで、メールの送受信などでは不具合がなくても、通信環境を見直すことをおすすめします。
と言うのも、オンライン商談はメールとは通信量が比ではないほど多いからです。
通信にかかるコストも増えますので、無制限に使えるものがよいでしょう。
また、スムーズに商談を進められるよう、通信速度の速いものを選ぶことも忘れないでください。
通信会社に問い合わせて、「オンライン商談ができる環境を整えたい」と相談してみてください。
【営業マン】オンライン商談のデメリット3つと対策法

前章までで、会社にとってのオンライン商談を導入するデメリットを紹介しました。
デメリットはありますが、対策をすればオンライン商談を活用できるので、ぜひ実践してみてください。
続いて、営業マンにとってのデメリットを3つ紹介します。
- 慣れるまで大変
- 身ぶりが伝わりづらい
- 信頼を得にくい
通常の商談でやっていることを、そのままオンライン商談で使っても商談はうまくいきません。
もちろん、商談の基本は変わらないので、今まで積み上げてきたスキルは大いに役立つでしょう。
しかし、オンライン商談ならではの特徴を知っておかないと、チャンスを逃してしまいます。
オンライン商談をうまくこなすコツも併せて紹介しますので、参考にしてください。
【営業マン】オンライン商談のデメリット①慣れるまで大変

オンライン商談を取り入れてすぐは、ツールの使い方を覚えることに追われます。
「どう振舞ったらうまくいくか?」などと考える前に、ツールの操作を覚えるだけで手一杯になるでしょう。
ただ、車の運転を覚えるように、回数を重ねていけば自然と覚えられるものなので、そこまで心配する必要はありません。
「どうしても心配」という人は、操作が簡単で画面がわかりやすいツールや、使い方を教えてもらえるツールを選びましょう。
【営業マン】オンライン商談のデメリット②身ぶりが伝わりづらい

オンライン商談では、映像が平面に見えるため、身ぶりが伝わりにくくなります。
とくに、うなずく場合にはかなりオーバーにやらなければ、相手に伝わりません。
どんな感じなのか知りたい人は、スマートフォンやパソコンの画面側にあるカメラを使ってみてください。
撮影しなくてもよいので、自分を画面に映しながら身ぶりをしてみましょう。
対面で受ける印象とはまるで違うことを実感できると思います。
このように、オンライン商談をする時には「オーバーリアクションかな?」と感じるくらいの身ぶりで丁度よいのです。
カメラで自分を映しながら、練習してみてください。
【営業マン】オンライン商談のデメリット③信頼を得にくい

オンライン商談では、対面営業に比べて人と話している感覚が薄くなる性質があります。
そのため、成約を勝ち取るために欠かせない信頼を得にくくなってしまいます。
対策としては、「当社では〜」よりも「私としては〜」などと、営業マン自身を意識させる言い回しを使うなどが挙げられるでしょう。
また、資料で数値データを強化し、より信頼性のある営業トークができるよう工夫してみてください。
表やグラフなどを使うと、見栄えがよくなるので顧客にも響きやすくなるでしょう。
ここまで、オンライン商談のデメリットとコツを紹介してきました。
オンライン商談にはメリットもたくさんある

ここまで、オンライン商談のデメリットを紹介してきました。
「思ったより多かった」と感じた人もいるかもしれません。
しかし、オンライン商談にはメリットもあります。
- コスト削減できる
- 見込み客が増える
- 顧客に使える時間が増える など
以上にあげたのはほんの一部ですが、このほかにも収益を伸ばすことにつながるメリットが複数あります。
オンライン商談にはツールが必要

オンライン商談をするにはツールが必要ですが、ツールにはさまざまな種類があり、条件によって選ぶべきものが異なります。
そのため、「どうやって選んだらよいかわからない」「なにが自分に合っているかわからない」と悩んでしまうかもしれません。
まとめ:対策をしてオンライン商談のデメリットを乗り越えよう

オンライン商談のデメリットについて紹介してきました。
重要な箇所をまとめてみましたので、最後に確認しておきましょう。
会社のデメリットと対策
- 社内に浸透しにくい
- 事前に告知する
- 使い方を指導する
- 顧客からの理解が必要
- 操作が簡単なツールを選ぶ
- 事前に挨拶に行く
- 通信環境の整備が必要
- 通信会社に相談する
営業マンのデメリットと対策
- 慣れるまで大変
- 数をこなして慣れる
- サポートしてくれるツールを選ぶ
- 身ぶりが伝わりづらい
- カメラの前で練習する
- 信頼を得にくい
- 一人称を使う
- 数値データを強化する
オンライン商談のデメリットは、以上のように対策することでトラブルを回避できます。
ツール選びが重要な箇所もあるので、トラブルになるリスクを避けたい場合は、ツール選びに気を配ってください。