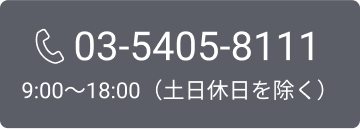RPAと連携可能なシステムとは?おすすめシステムやメリットデメリットを紹介

「RPAを導入したいけれど、どんなシステムと連携できるのかな?」「RPAを活用するとどんなメリットがあるの?」とお悩みではありませんか?
業務効率化やコスト削減を目指しながらも、具体的な導入方法や連携可能なシステムがわからずに困っている方も多いのではないでしょうか。
RPAは多種多様なシステムと連携することで、その効果を最大限に発揮しますが、適切な選択と運用が必要不可欠です。
そこで本記事では、RPAと連携可能なシステムや、導入のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
この記事を読むことで、RPAを活用した業務効率化の具体的なイメージをつかめるようになり、導入時の注意点を理解できるようになります。ぜひ最後までご覧ください。
RPAと連携可能なシステム

RPAは、多種多様な業務システムと連携できる柔軟性が特徴です。
以下に、とくに連携効果が高いシステムを8つ紹介します。
- ・ERPシステム
- ・CRMシステム
- ・AI-OCR
- ・会計ソフト
- ・ワークフロー管理ツール
- ・メールシステム
- ・BIツール
- ・ECプラットフォーム
ERPシステム
ERPシステムは、販売管理・在庫管理・会計管理を一元化し、リアルタイムのデータ連携で部門間の情報共有を効率化する基幹システムです。
RPAと連携することで、大量のデータ入力やレポート作成を自動化し、業務効率を大幅に向上させます。
リアルタイムでのデータ統合により、状況把握が迅速化し、部門間連携が強化されるほか、プロセスの標準化によって経営判断のスピードと正確性も向上します。
ただし、導入・運用コストが高く、カスタマイズが必要になる場合が多い点には注意が必要です。
CRMシステム
CRMシステムは、顧客管理や営業活動を効率化するためのプラットフォームです。
RPAと連携することで、問い合わせ対応や顧客データの更新が自動化され、担当者の負担軽減と顧客満足度の向上を実現します。
また、購買履歴や行動履歴の分析により、適切なタイミングでのフォローが可能になる点も大きな強みです。
企業規模や業種によっては導入コストが高くなるため、必要な機能を慎重に選定することが重要です。
AI-OCR
AI-OCR(Optical Character Recognition/Reader)は、紙書類をデジタルデータに変換する技術で、RPAと組み合わせることでアナログ業務を効率的に自動化できます。
たとえば、以下のようなフローが実現可能です。
- ・郵送やFAXで届く注文書や請求書をAI-OCRでデジタル化
- ・データ化した情報をRPAで基幹システムに自動入力
- ・RPAを活用して注文受付や完了通知メールを自動送信
これらのプロセスを自動化することで、担当者は誤入力や例外対応などの個別ケースに集中でき、業務全体の効率が大幅に向上します。
会計ソフト
会計ソフトは、仕訳登録・請求書管理・決算処理を一元化し、紙作業を削減して業務効率化を実現するツールです。
RPAと連携することで、銀行明細の自動取得や仕訳入力が自動化され、経理担当者の負担軽減と人的ミスの防止が可能です。
さらに、リアルタイムで財務状況を把握でき、迅速な経営判断を支援してくれます。
ワークフロー管理ツール
ワークフロー管理ツールは、業務プロセスやタスクの進行状況を可視化・自動化するシステムです。
代表的なツールには「Trello」「Asana」「kintone」などがあり、タスクをカード形式で管理し、リアルタイムで進捗を共有できます。
RPAと連携することで、承認フローや報告作業を自動化し、確認や通知を効率的に行えるため、意思決定のスピードが向上します。
また、タスクの抜け漏れを防ぎ、重複作業を削減することで、チーム全体の生産性を向上させるのも大きなメリットです。
メールシステム
メールシステムはビジネスに欠かせないコミュニケーションツールの1つで、有名なものだと「Outlook」や「Gmail」が広く利用されています。
RPAと連携することで、定型文の自動返信や大量のメール振り分けが可能になり、作業時間を短縮しつつ、重要な案件に集中できる環境を整えられます。
また、添付ファイルの自動ダウンロードや社内システムへの格納を自動化することで、時間と手間を大幅に削減可能です。
スパムメールの管理やメール紛失の防止にも役立つため、情報漏えいリスクを軽減しつつ、安定した運用をサポートしてくれます。
BIツール
BI(Business Intelligence)とは、企業内外のデータを分析・可視化するためのシステムです。
代表的なツールには「Tableau」や「Power BI」などがあります。
RPAと連携することで、データ収集やレポート更新といった定型的な作業を自動化でき、担当者はデータ分析や戦略立案といった付加価値の高い業務に専念できます。
また、レポートやグラフが自動的に更新されるため、常に最新の情報を基に判断を下せる点も大きな利点です。
ただし、扱うデータ量が増えるほど設計や運用が複雑化するため、導入時には要件定義やデータガバナンスを徹底することが重要です。
ECプラットフォーム
ECプラットフォームはネットショップの構築や運営を支える基盤で、「Shopify」や「EC-CUBE」に加え、「Amazon」「楽天市場」などのモール型サービスも含まれます。
RPAと連携することで、商品登録・在庫更新・受注処理・発送状況の管理といった業務を自動化でき、作業負担の軽減やヒューマンエラーの防止が期待されます。
また、顧客データや売上情報をリアルタイムで取得することで、在庫不足を早期に検知し、迅速な対応が可能です。
さらに、キャンペーン情報の更新やレビューへの返信といった作業も効率化され、業務全体のスピードアップが図れるだけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。
RPAを連携するメリットとデメリット

この章では、RPAと別システムを連携する際のメリットとデメリットについて解説します。
- メリット①:複雑な手順を要する業務を簡略化できる
- メリット②:処理の精度とスピードを大幅に改善できる
- デメリット①:エラー発生時に業務が停止する恐れがある
- デメリット②:業務内容が不透明になりやすい
メリットデメリットを把握しておくことで、業務プロセスの効率化や導入効果を最大化するための判断材料として役立つでしょう。
メリット①:複雑な手順を要する業務を簡略化できる
RPAを導入し、Excelや会計システムなどを連携させることで、これらのシステム間にまたがる業務を効率的に自動化することが可能です。
初期設定こそ必要ですが、一度設定が完了すれば、担当者はRPAが処理した結果を確認するだけで済むため、日々の作業負担を大幅に軽減できます。
たとえば、1名のパートスタッフが月160時間かけて行っていた事務作業をRPAで自動化すると、月10時間程度の確認作業のみで済むようになります。
これにより、時給1,200円の場合、月約19万円の人件費が約1万2千円に削減可能です。
メリット②:処理の精度とスピードを大幅に改善できる
RPAツールと連携することで、業務の精度と処理速度を大幅に向上させることが可能です。
RPAは設定された手順を忠実に実行し、人的ミスを完全に排除するため、データ処理や業務内容の正確性が格段に高まります。
さらに、RPAは24時間365日稼働可能なため、作業を時間や人員に依存することなく迅速に進めることが可能です。従来は時間を要していた反復作業や大量のデータ処理も短時間で完了し、業務の効率化が実現します。
こうした特性により、業務の信頼性が向上するとともに、処理速度の向上による業務全体の生産性アップが期待できます。
デメリット①:エラー発生時に業務が停止する恐れがある
RPAを導入することで多くのメリットが得られる一方で、注意が必要な課題も存在します。
その代表的な例が、エラー発生時に業務が停止するリスクです。
RPAツールは複数のシステムをまたいで業務を自動化するため、エラーが発生すると連携しているシステム全体に影響を及ぼす可能性があります。このような状況では、エラーが解消されるまで業務が停滞し、運営に支障をきたすことが懸念されます。
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、自動化ロボットの導入後に、範囲を限定したテスト運用を行い、動作確認とエラー修正を徹底することが重要です。この段階で問題点を洗い出し、対策を講じることで、安定した運用を実現できます。
さらに、RPA提供元が提供する導入サポートを活用することで、初期設定や運用準備をスムーズに進めることが可能です。専門家のアドバイスを受けることで、運用開始後のトラブルを未然に防ぎ、安心して運用を進めるための体制を整えられます。
これらの対策を講じることで、RPA導入に伴うリスクを軽減し、効率的で安定した運用が可能になります。
デメリット②:業務内容が不透明になりやすい
RPAで業務を自動化すると、担当者が離職した際に業務内容がブラックボックス化するリスクがあります。
一見問題がないように見えても、作業フローの見直しが難しくなり、業務改善の機会を逃してしまうことがあります。また、RPAが停止した際に代替手段がないと、業務全体が滞る可能性も否めません。
こうしたブラックボックス化を防ぐには、自動化前の作業プロセスをマニュアル化し、手動対応ができる体制を整えることが重要です。加えて、離職時の引き継ぎを徹底し、RPA設定を定期的に見直すことで、運用の安定性を確保できます。
これらの対策を適切に講じることで、業務の透明性を維持しつつ、RPA導入の効果を最大限に活用することが可能になります。
RPA連携の流れ

RPAを導入する際は、以下のステップに沿って進めるのが一般的です。
- 計画と設計
- テスト導入
- 本格導入
- 運用と保守
各手順について、詳しく解説します。
計画と設計
RPA導入の準備段階では、自動化する業務を選定し、それを実行するロボットを作成する作業が重要です。
タスクマイニングツールを活用したり、各部署にヒアリングを行ったりして、単純作業ながら工数や時間を多く要している業務を洗い出しましょう。
初期段階では、現場がRPAの可能性を十分に理解しておらず、自動化に適した業務が提案されないケースもあります。「RPAで何ができるか」が曖昧なため、業務の自動化をイメージしづらく、提案が止まってしまうのが原因です。
これを防ぐには、「工数が多い業務」や「単純だが手間がかかる作業」を例に挙げて意識的に収集を進めることが効果的です。
こうしたアプローチにより、効率化の余地が大きい業務を明確にし、自動化による成果を最大化できる準備が整います。
テスト導入
テスト導入の段階では、まず最小限の範囲でRPAを試験的に稼働させ、問題なく動作するか確認します。
具体的には以下の2点をチェックします。
- ・エラーが発生していないか?
- ・指示内容に誤りがなく、アウトプットが正確か?
これらに問題があれば、修正を繰り返し、完全に動作が安定するまで調整を行います。
テスト段階をクリアした後は、導入範囲を拡大するために、全体導入によって業務効率がどの程度向上するか、また導入後の業務フローや作業分担がどのように変化するかを検討する必要があります。
これらを基に、RPAを活用した最適な業務フローや人員配置を計画することが重要です。
さらに、無料トライアルを活用することで、コストを抑えながらテスト導入を実施でき、初期段階での負担を軽減することが可能です。
本格導入
テスト導入が成功したあとは、実際の業務にRPAを組み込み、ロボットが決まった時間に自動的に稼働するようスケジュールを設定します。
本格導入後も、業務効率化の成果を定期的に測定し、具体的な改善効果を記録することが重要です。
さらに、現場でスムーズに運用を進めるためには、操作マニュアルや運用ルールを整備し、従業員がRPAを活用しやすい環境を構築することが求められます。
これにより、RPAの効果を最大限に引き出すことが可能になります。
運用と保守
運用開始後は、エラーの有無を定期的に確認するとともに、さらなる効率化の余地がないかを継続的に検討することが重要です。
業務フローに変更が生じた場合は、それに合わせてロボットの設定を見直し、適切に対応しましょう。
また、業務のブラックボックス化を防ぐため、従来の業務フローやロボットの設定内容をマニュアル化しておくことが必要です。
これにより、運用の透明性を保ちながら、トラブル時の迅速な対応が可能になります。
RPAの選び方の注意点

RPAは、多様なシステムやツールと連携し、幅広い業務の自動化を実現できる強力なツールです。
ただし、導入を成功させるためには、以下の3つのポイントに注意が必要です。
- ・既存システムとの互換性
- ・自社業務に適したRPAの選定
- ・セキュリティ対策の確認
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
既存システムとの互換性
RPAはさまざまなシステムと連携可能ですが、導入前に自社の既存システムやツールと問題なく連携できるかを確認することが重要です。
そのため、本格的な導入に先立ち、無料トライアルを利用して実際に動作を検証するのがおすすめです。
無料トライアル期間中は、ツールを一定期間無料で利用できるため、操作性や細かい機能など、公式サイトや資料だけではわからない部分を実際に試して確認できます。
このプロセスを通じて、RPAが自社のニーズに適しているかをより具体的に評価できるでしょう。
自社業務に適したRPAの選定
RPAには、サーバー型・デスクトップ型・クラウド型の3つの導入形態があり、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットを持っています。
自社の業務内容、規模、予算に合わせて最適な形態を選ぶことが成功の鍵となります。
以下に、それぞれの特徴をまとめました。
| サーバー型 | 自社サーバーで運用し、セキュリティ管理やシステム連携に優れるが、導入コストが高く管理負担が大きい。 |
| デスクトップ型 | パソコン1台で手軽に導入可能で低コストだが、対応範囲が限定され、システム連携に制約がある。 |
| クラウド型 | サーバー管理が不要でクラウドサービスとの連携が容易だが、月額費用が発生しセキュリティはベンダー依存となる。 |
これらの特徴を正しく理解し、自社のニーズに合わせて選定することで、業務効率化を最大化し、RPA導入の効果を高められるでしょう。
セキュリティ対策の確認
RPAを他のシステムと連携する際には、顧客や取引先、自社の従業員などの情報を自動で処理・管理するため、セキュリティ対策が不可欠です。システムに脆弱性があったり設定ミスがあると、サイバー攻撃を受けて情報漏洩が発生するリスクが高まります。
情報漏洩が起これば、企業の信頼低下や損害賠償に発展するだけでなく、システム破壊や業務停止といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため、RPA導入時には、ベンダーが提供するセキュリティ対策を事前に確認することが重要です。
具体的には、データの暗号化が実施されているか、作業ログを記録する仕組みがあるかを確認しましょう。また、自社内でもアクセス権限を適切に設定し、定期的なシステムアップデートを行うことでセキュリティを強化する必要があります。
これらの対策を徹底することで、RPA導入に伴うリスクを最小限に抑え、安全かつスムーズな運用が可能になります。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

RPAツールの選定において、操作性やサポート体制、コストパフォーマンスは重要な要素です。
『おじどうさん』は、これらの点で優れた特徴を持つRPAツールとして注目されています。
『おじどうさん』のおすすめポイントは以下のとおりです。
| 学習コストの低さと高い導入成功率 | ユーザーフレンドリーな設計により、短期間での習得が可能で、導入成功率が高いと評価されています。 |
| 安定したロボット動作 | 動作の安定性が高く、メンテナンスにかかる時間を最小限に抑えられます。 |
| 充実した機能とサポート | ユーザーのニーズに応じた機能やサポート体制が整っており、安心して利用できます。 |
| 実績と信頼性 | 多くの現場での導入実績があり、業務効率化に成功している事例が多数報告されています。 |
これらの特徴により、『おじどうさん』は初めてRPAを導入する企業から既存のRPA環境を見直したい企業まで、幅広いニーズに対応できるツールとしておすすめできます。
業務の自動化を検討されている方は、ぜひ『おじどうさん』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ

本記事では、RPAと連携可能なシステムや、導入のメリット・デメリット、そして具体的なツールとして『おじどうさん』について解説しました。
RPAは業務効率化やコスト削減に大きな効果を発揮する一方で、システム連携やセキュリティ対策が不十分な場合、業務停止や情報漏洩といったリスクが生じる可能性もあります。
しかし、こうしたリスクは適切なツール選定や運用体制を整えることで、十分に回避可能です。
RPAの導入は一度の施策で終わるものではなく、運用後の改善や活用の幅を広げていくプロセスが重要です。適切な対策と計画を講じ、RPAの効果を最大化していきましょう!