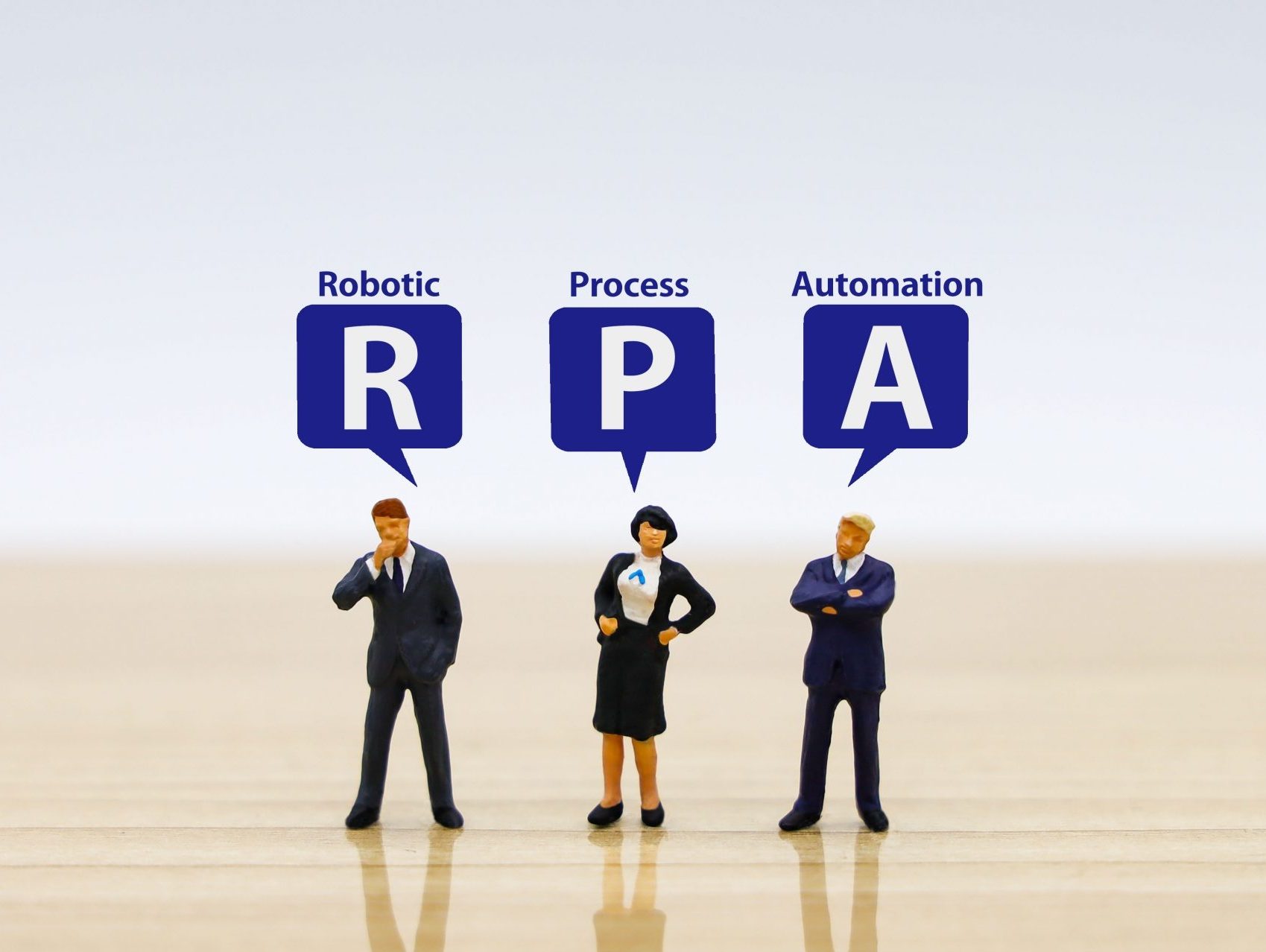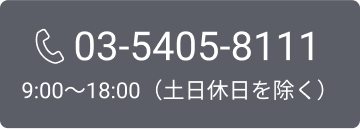RPAとマクロの違いは?共通点や活用シーンも紹介

「RPAとマクロの違いって何だろう?」「どちらを選ぶべきなの?」とお悩みではありませんか?
業務の効率化や自動化を進めるうえで、RPAやマクロといったツールは非常に便利です。しかし、具体的にどのように使い分けるべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
RPAはより高度な業務自動化を実現できる一方で、マクロは特定のツールに特化した手軽な自動化を可能にします。
そこで本記事では「RPAとは何だろう?」「マクロやVBAとの違いは何か?」といった疑問を解消し、さらに具体的な活用シーンまで詳しく解説します。
この記事を読むことで、RPAとマクロを業務にどう活用すべきか明確になり、最適な選択ができるようになるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
【この記事の内容】
RPAとは何か
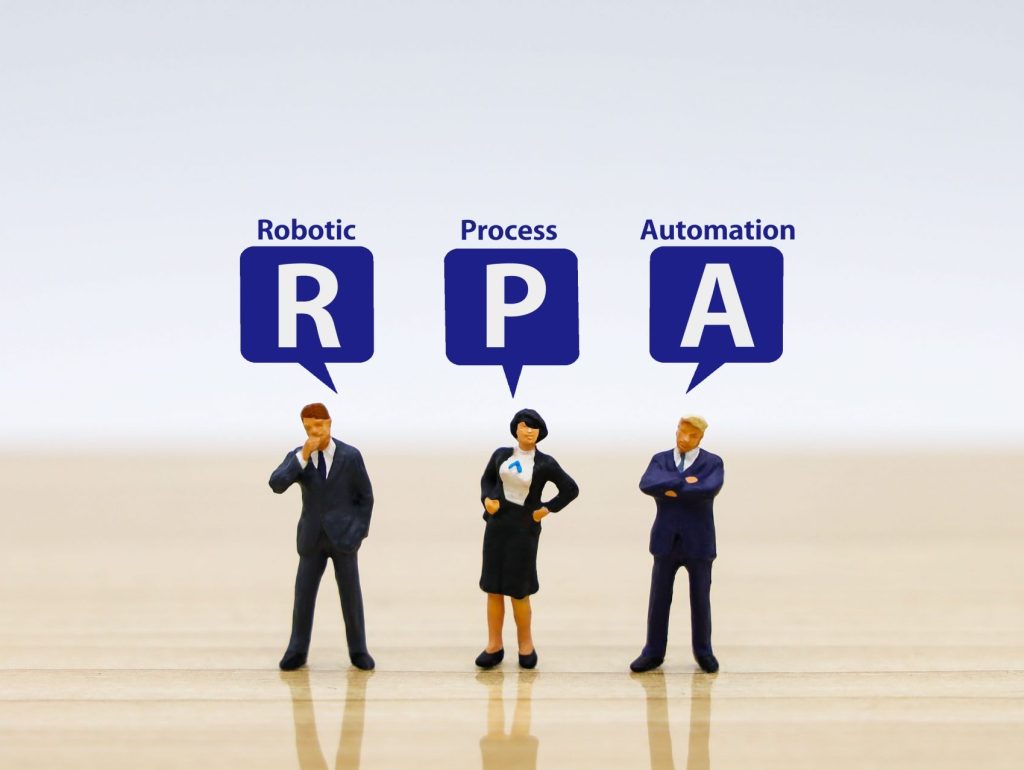
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、事務作業などの定型業務を自動化するためのソフトウェアロボットを指します。
データ入力や転記、レポート作成といった単純作業を正確かつ効率的に処理し、人間の手を借りずに繰り返し実行することが可能です。
製造業や金融業、医療業界など幅広い分野で導入が進んでおり、業務効率化・ヒューマンエラーの防止・人手不足の解消といった課題解決に役立っています。
プログラミング知識がなくても使用可能で、直感的な操作で利用できるノンコーディング対応のツールも多いため、多くの企業から注目されているツールの1つです。
マクロとは何か

マクロとは、ExcelやWordなどのMicrosoft Office製品に組み込まれた機能で、特定の操作を記録し、ワンクリックで再実行できる自動化ツールです。
たとえば、Excelでのデータ入力や数式設定、グラフ作成などの繰り返し作業をボタン1つで効率よく処理できます。プログラミングの知識が不要で、記録機能を使うだけで簡単に設定できるため、日常的な事務作業を大幅に簡略化できます。
一方、操作の範囲が限定されているため、複雑な条件分岐や動的処理には向きません。マクロは、データ処理の効率化や人的ミスの軽減に役立つ実用的なツールとして、多くのビジネス現場で活用されています。
VBAとは何か

VBAとは(Visual Basic for Applications)の略で、Microsoft Office製品の操作を自動化するためのプログラミング言語です。
マクロよりも柔軟で高度な機能を備え、条件分岐や繰り返し処理、データベースとの連携といった複雑な処理も可能です。
たとえば、Excelで大量のデータを自動的にフィルタリングして別のシートに整理したり、複数のOfficeアプリケーションを連動させて作業を一括処理することができます。
プログラミングスキルは求められるものの、業務効率や正確性を大幅に向上させることが可能なため、エンジニアだけでなく事務職やデータ分析に携わる人々にも広く活用されています。
RPAとマクロは何が違うのか

ここまで、RPA、マクロ、VBAの違いを解説してきました。それでは、RPAとマクロの違いはどこにあるのでしょうか?
主な相違点は以下の4つに集約されます。
- ・導入プロセスとコスト
- ・自動化可能な業務の範囲
- ・プログラミングスキルの必要性
- ・処理できるデータ容量
自動化可能な業務の範囲
RPAとマクロはどちらも定型作業の自動化に役立ちますが、自動化の対応範囲には大きな違いがあります。
マクロは主にExcelなどのMicrosoft Officeアプリ内で動作し、VBAを活用した場合でも、Microsoft製アプリの範囲を超える作業の自動化はできません。
一方で、RPAはOfficeアプリに限らず、さまざまなアプリやシステムを連携させて業務を自動化できます。
Webサイトからダウンロードしたデータを基にExcelでグラフを作成したり、ファイルをチャットツールで共有したりといった、複数のアプリケーションをまたぐ作業もRPAなら簡単に自動化できます。
RPAを活用することで、従来の方法では難しかった幅広い業務の効率化が実現し、企業全体の生産性向上につながるでしょう。
プログラミングスキルの必要性
RPAもマクロも、作業を自動化するには最初に人間が動作を指定する必要があります。ただし、指定方法や必要なスキルには違いがあります。
マクロの場合、VBAというプログラミング言語を用いて動作を指定するため、VBAの知識が必須です。コードを書くことで自動化する内容を細かく設定できるため、プログラミングスキルが重要な要素となります。
一方、RPAはツールによってはプログラミング知識がなくても利用できるケースが多いのが特徴です。しかし、複雑な作業の自動化やトラブル時の対応などを行う際には、プログラミングの知識があると効率よく対応できるでしょう。
処理できるデータ容量
RPAは、定型化された繰り返しの業務において、業務効率を大幅に向上させるツールです。
Excelマクロは、使用するパソコンのスペックに大きく依存します。そのため、スペックが低い場合には、大量のデータを処理する際に動作が遅くなったり、フリーズすることがあります。
RPAのうちデスクトップ型も、パソコンにインストールして使用するため、同様にパソコンの性能が不足していると処理がスムーズに進まない場合があります。
一方で、サーバー型やクラウド型のRPAは、データ処理をサーバーやクラウド上で実行するため、パソコンのスペックに左右されず、大量のデータも高速かつ安定して処理できるのが特徴です。
導入プロセスとコスト
ExcelマクロはExcelに標準搭載されている機能のため、追加のツールやシステムを導入する必要がなく、Excelさえあればすぐに自動化を始めることができます。
これにより、別途費用が発生しない点が大きなメリットです。
一方、RPAはベンダーが提供するさまざまなツールの中からライセンスを購入する形で導入します。RPAにはデスクトップ型・サーバー型・クラウド型といった種類があり、それぞれ費用が異なります。
一般的に、デスクトップ型やクラウド型は数十万円〜数百万円、サーバー型は数百万円以上の費用がかかるとされています。
導入の際には、自社のニーズに合ったツールを選び、費用対効果をしっかりと検討することが重要です。
RPAとマクロの3つの共通点

これまで紹介してきたように、RPAとマクロにはさまざまな違いがある一方で、共通点も多くあります。
以下に、RPAとマクロの3つの共通点を挙げます。
- ・非定型業務の自動化には向かない
- ・作業ミスのリスクを軽減
- ・定期的な管理や更新が必要
「定型作業の自動化」以外にどのような共通点があるのかを、具体的に解説します。
非定型業務の自動化には向かない
RPAとマクロは、いずれも定型作業の自動化を得意としていますが、非定型業務の自動化には不向きです。
これは、作業手順が事前に決められたプロセスを、その通りに実行・反復する仕組みに基づいているためです。
ただし、RPAについてはAIとの組み合わせが進んでおり、特定のツールでは一部の非定型業務にも対応可能な機能が提供されています。
これにより、RPAの適用範囲が今後さらに広がる可能性もあります。
作業ミスのリスクを軽減
RPAとマクロは、繰り返し作業や時間のかかる業務を効率化し、高速かつ正確に処理できるツールです。
人間の作業では、疲労や集中力の欠如によってミスが発生するリスクがありますが、RPAやマクロは設定された手順通りに実行するため、ミスが発生することがありません。
その結果、業務の正確性が向上し、作業ミスによるトラブルや手戻りを防ぐことができます。
定期的な管理や更新が必要
RPAとマクロは設定した手順通りに作業を自動化できますが、アプリやシステムが変更されるとエラーが発生し、再設定が必要になることがあります。
そのため、導入時からメンテナンスがしやすい設計にしておくことが大切です。また、担当者が変わる際には、設定内容や運用ルールをしっかり引き継ぎ、管理体制を整える必要があります。
これらの準備をしておくことで、長期的にスムーズな運用が可能になるでしょう。
RPAを活用できるシーン

RPAは、多様な業界で業務効率化に活用されています。
たとえば金融業界では、口座開設時の顧客情報入力や請求書処理の自動化に利用され、手作業によるミスを削減しつつ処理速度を向上させます。
製造業では、在庫管理データの更新や生産レポートの作成に活用され、リアルタイムでの情報把握が可能です。
さらに、医療業界では患者データの管理やスケジュール調整、電子カルテの処理に使用され、事務作業の負担を軽減可能です。
ECサイト運営においても、注文データの管理や在庫状況の更新、配送手配の効率化にも役立っています。
このように、RPAはさまざまな業界や業務で、時間削減と正確性の向上を実現しています。
マクロを活用できるシーン

マクロは、Officeアプリケーション内の定型業務を効率化するために広く利用されています。
たとえば、Excelでは大量のデータを自動で集計したり、特定の条件に基づいてフィルタ処理を行ったりする作業に活用されます。また、定型フォーマットのレポートを自動生成したり、複雑なグラフを短時間で作成することも可能です。
繰り返し行うデータ入力や書式設定を自動化することで、作業時間を大幅に短縮でき、ミスを防ぐ効果も得られます。
ただし、マクロの作成やカスタマイズにはVBAの知識が必要になる場合があるため、設定時にはプログラミングスキルを持つ人材が必要不可欠です。
業務効率化ツールを導入するなら『おじどうさん』

『おじどうさん』は、ブルーテック株式会社が提供するRPAツールで、業務の自動化と効率化をサポートしてくれます。
プログラミング知識がなくても直感的な操作が可能で、ITリテラシーに不安がある方でも簡単に扱えます。
さらに、導入支援や問い合わせ対応といった手厚いサポートが追加費用なしで受けられるため、RPA導入が初めての企業でも安心してスタートできるでしょう。
料金は月額8万円と手頃で、初期費用も10万円と抑えられているため、中小企業にも導入しやすい点がポイントです。
このツールを導入することで、定型的な事務作業を効率化し、手作業によるミスを減らしながら業務の正確性を向上させることが可能です。結果として、企業全体の生産性向上や人件費の削減、残業時間の短縮といった効果も期待できるでしょう。
業務効率化ツールを検討中の企業にとって『おじどうさん』は信頼できる選択肢の1つです。
ぜひ導入候補として検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ

本記事では、RPAやマクロの違いや共通点、それぞれの活用シーンを解説しました。
RPAは幅広い業務の自動化に対応できる一方で、導入コストが高いという課題があります。一方、マクロは低コストで利用を開始できるものの、自動化できる範囲が限定される点に注意が必要です。
どちらも定型業務の効率化には効果的ですが、業務内容や目的によって最適な選択が異なります。そのため、RPAとマクロの特性をしっかりと理解し、自社に適した活用方法を検討することが重要です。
メリットとデメリットを比較したうえで、自動化ツールをうまく活用し、業務効率を最大化していきましょう!