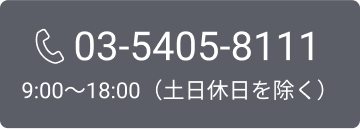定型業務とは?種類やRPA導入での効率化について解説

企業活動には、日々繰り返し行う定型業務と呼ばれる作業が数多く存在します。なかでも事務処理やデータ入力などは負担になりやすく、効率化を図るうえで見逃せないポイントです。本記事では、定型業務の概要と具体例、さらにRPA導入などによる効率化策をわかりやすく解説し、生産性向上につなげるためのヒントを紹介します。
この記事を読むことで、業務効率の改善に役立つポイントを理解できます。日々の業務負担を軽減したい方や、業務改善に取り組む企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事の内容】
定型業務とは

定型業務とは、手順や手続きがあらかじめ定まっている反復的な作業を指します。具体的には、請求書の発行や在庫データの集計などが典型例といえます。同じ手順を繰り返すため、作業工程をマニュアル化しやすい反面、担当者の負担が大きくなりがちです。
その一方で、定型業務は仕組み化が行いやすい特徴があります。近年では、電子化やRPAツールが普及している影響で、入力作業や転記業務をシステムに任せるケースが増えました。従来、人の手で処理していた作業を自動化できれば、人為的なミスや作業時間を削減できる点が大きなメリットといえます。
とくにデータ入力作業はRPA導入が進み、ルールを自動実行できるため、効率化が期待できます。
非定型業務との違い
非定型業務は、決まった手順がなく、その都度の判断や専門知識が求められる業務です。市場調査や戦略立案・クライアントとの折衝・カスタマーサポートの高度な対応、プロジェクトの進行管理などが代表的で、状況に応じた柔軟な対応が必要になります。
一方、定型業務は同じ作業を繰り返すため、マニュアル化や最適化がしやすいという特徴があります。RPAによる効率化が可能な業務と、人が対応すべき業務を適切に切り分けることが重要です。
定常業務との違い
定常業務とは、企業や組織で毎日・毎週・毎月などの周期で、定期的に実施される作業のことです。たとえば、日次の売上確認や週次ミーティングなどが挙げられます。一見すると、定期的に繰り返される点で定型業務と似ていますが、 必ずしも手順が固定されているわけではありません。そのため、定常業務のなかには非定型的なタスクが含まれることもあります。定型業務が細分化された手順どおりに進めやすいのに対し、定常業務は日々の状況に応じてアレンジが必要な場合もあることが特徴です。
RPAを導入する際には、 定常業務のなかでも定型化できる部分を見極め、効率的に自動化を進めることが重要です。
通常業務との違い
通常業務とは、日常的に行われる業務全般を指す広い概念です。定型業務や非定型業務、定常業務などを含むため、一括りに説明するのは難しい面があります。あくまで「日頃の業務」という意味合いが強く、具体的な作業手順の有無を問いません。そのため、定型業務のように明確なルールがある作業だけでなく、イレギュラー対応も通常業務に含まれます。ここが定型業務との大きな差であり、業務範囲が広いぶん、すべてを自動化するのは難しいといえます。
RPAを導入する際には、通常業務のうち反復性が高い部分を特定し、定型化できる領域を優先的に効率化すると効果的です。そのためには、人の判断が求められる業務と、ルール化できる業務を適切に切り分けることが重要です。
定型業務の具体例

定型業務には、請求書や見積書の作成、在庫や売上データの集計、各種システムへの情報入力などが挙げられます。これらは手順が明確で、決まった操作を繰り返すことで完了する点が特徴です。
また、受発注管理やレポート作成といったルーチンワークも、RPAを活用することで自動化が可能になり、担当者の負担を大幅に軽減できます。こうした業務はマニュアル化しやすく、ツールを導入することで生産性の向上が期待できるでしょう。
業務を定型化することのメリット
業務を定型化することで作業手順が明確になり、担当者の混乱を防ぐだけでなく、業務の属人化も抑えられます。さらに、定型化された手順をRPAに組み込むことで自動化が可能となり、人為的ミスの大幅な削減につながります。これにより、単なる効率化にとどまらず、業務フローの可視化が進み、課題の発見や改善にも役立つでしょう。
導入コストを抑えながら高い効果が期待できるため、中小企業においても積極的に導入が進んでいます。生産性の向上と業務効率化を同時に実現できることこそ、業務定型化の最大の魅力といえるでしょう。
業務を定型化することのデメリット
業務を定型化すると、変化への対応が遅れるリスクがある点が課題です。環境や顧客ニーズが変化した際、マニュアルやシステムの見直しが必要になり、柔軟に対応しづらくなることが考えられます。
また、定型業務に依存しすぎると、担当者の判断力や創造力が育ちにくくなる恐れもあります。マニュアル外のトラブルが発生すると、適切な判断ができず、業務全体の停滞を招くこともあるでしょう。
さらに、予測不能な変化や突発的な課題には対応しきれない側面もあります。定型化を進める際は、業務の特性を見極め、柔軟に見直しを行うことが重要です。
定型業務を効率化する方法は?

定型業務の効率化には、RPAをはじめとする自動化ツールの活用がカギとなります。以下からは、具体的な効率化手段を3つ紹介し、それぞれの特徴やRPA導入のポイントについて解説していきます。
- ・マニュアル化とテンプレートの活用
- ・業務フローの見直しとタスク統合
- ・部分的なアウトソーシングの活用
マニュアル化とテンプレートの活用
マニュアル化とテンプレートの活用は、定型業務を効率化するうえで欠かせない手法です。作業手順を文書化し、常に最新の情報へ更新することで、担当者間の認識のズレを防ぎやすくなります。また、請求書や見積書などの書類をテンプレート化すれば、入力ミスの削減や処理のスピードアップも期待できるでしょう。
さらに、RPAを導入する際には、標準化された手順やフォーマットがあることで、自動化の実装がスムーズに進みます。とくに、文書作成やデータ転記といった業務はRPAソフトウェアが得意とする分野であり、人手による確認作業を大幅に削減できる点が強みです。
結果として、業務の属人化を防ぎつつ、安定した品質を維持しやすくなります。
業務フローの見直しとタスク統合
業務フローの見直しとタスク統合も効果的なアプローチです。どのタイミングでどの情報が必要かを整理し、不要なステップを削減するとともにまとめられる作業を統合することで、業務全体のスムーズな流れを実現できます。
RPA導入時には、あらかじめ最適化されたフローを設定することで、ロボットが実行する処理範囲を明確化できます。たとえば書類提出から承認、データ入力までを一貫して自動化するなど、人の手を介さない流れを確立できる点がメリットです。業務全体を最適化することで、定型業務の効率が向上し、より生産性の高い環境を実現できるでしょう。
部分的なアウトソーシングの活用
部分的なアウトソーシングも、定型業務の効率化を進めるうえで有効です。
たとえば、経理処理やデータ入力などの業務を専門の外部企業に委託することで、社内リソースをコア業務へ集中させることが可能になります。自社でRPAを導入するのが難しい場合でも、外部パートナーがロボットを活用していれば、その自動化のメリットを享受できるでしょう。
結果として、社内の人材をより付加価値の高い業務へとシフトさせ、生産性の向上につなげることが可能です。
定型業務を効率化させる際のポイント

定型業務を効率化する際は、導入コストと効果のバランスを考慮しながら、業務特性や社員のスキルに合わせた最適な手段を選ぶ必要があります。
ここでは、RPA導入を視野に入れつつ、注意すべき3つのポイントを紹介します。
- ・費用対効果を見極める
- ・社員のITリテラシー向上
- ・運用後の検証と改善を怠らない
費用対効果を見極める
RPAを導入する場合、ソフトウェアのライセンス費用や開発コストだけでなく、保守・運用にかかるコストも考慮することが大切です。高額なシステムを導入しても、対象業務のボリュームが小さいと十分な費用対効果が得られません。
そこで、まずは試験導入や小規模なプロセスを自動化し、成果を測定してから本格的に拡大する手順が安全策です。
社員のITリテラシー向上
新しいシステムやRPAを活用するには、社員が基本的なITリテラシーを身につけている必要があります。教育をおろそかにすると、設定ミスや運用トラブルが増える恐れがあります。定期的な研修やマニュアル整備を通じて知識を共有し、社員全体でスムーズに使いこなせる環境を整えることが重要です。
運用後の検証と改善を怠らない
RPA導入後も定期的に運用状況をチェックし、想定外のエラーや効率低下が起きていないか確認する必要があります。問題が見つかったら迅速に修正を行い、業務フローやロボットの動作を最適化し続けることで、効果を最大化できるのがポイントです。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

定型業務の効率化を進めるうえで、RPAの操作性やサポート体制は非常に重要なポイントです。そこで注目したいのが、ブルーテック株式会社が提供する『おじどうさん』です。『おじどうさん』の魅力は、プログラミング不要で直感的にロボットを作成できる点にあります。ITの専門知識がなくてもスムーズに導入できるため、現場レベルでの活用がしやすいのが特徴です。
また、ライセンスには導入支援や問い合わせ対応が含まれており、追加費用なしで充実したサポートを受けられます。官公庁や上場企業にも導入される高度なセキュリティも備え、安全性の面でも信頼できるツールです。業務の自動化をスムーズに進めるなら、『おじどうさん』の活用を、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
まとめ

定型業務は手順が明確で、RPAを活用することで大幅な効率化が可能です。
ただし、非定型業務やイレギュラー対応との切り分けが必要です。とくに『おじどうさん』は、プログラミング不要で直感的にロボットを作成できるため、ITスキルがない現場でもスムーズに導入できます。導入後のサポートも充実しており、運用面でも安心して活用できるのが大きな強みです。
適切な手法を選びながら導入を進めることで、企業全体の生産性向上や業務負担の軽減につながり、働き方改革の実現にも貢献できるでしょう。