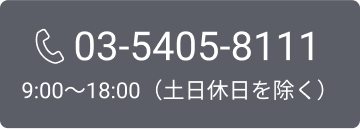4P分析とは何?4C分析・3C分析との違いや進め方、企業事例を解説

デジタル化が加速し、消費者のニーズが多様化する昨今、企業が市場で競争優位を確立するためには、戦略的なマーケティング施策が求められます。マーケティング戦略を効果的に実行するためには、適切な分析フレームワークの活用が不可欠です。
なかでも「4P分析」「4C分析」「3C分析」は、企業が市場環境や顧客ニーズを理解し、競争優位性を築くための基本的な手法として広く知られています。本記事では、これらの分析手法の違いや進め方、さらに具体的な企業事例を通じて、実践的な活用方法を解説します。マーケティング戦略の精度を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事の内容】
4P分析とは?基本を理解しよう

4P分析とは、マーケティングにおいて製品・価格・流通・販促の4つの要素を体系的に整理し、戦略を立案する方法です。これらはProduct・Price・Place・Promotionの頭文字を取った名称であり、とくに製品やサービスを市場に展開する際の基本視点になります。
企業は4つの角度から自社の強みを洗い出し、市場ニーズに適合する打ち手をまとめることが可能です。製品の特長と品質を吟味しながら価格を設定し、その後に流通チャネルをどう構築するかを検討する段階があります。最終的には販促活動を用いてターゲット層への認知を促し、購買意欲を高める流れを作れるでしょう。
マーケティング戦略における4Pの位置づけ・目的とは
4P分析は、市場環境を踏まえた具体的施策を整理する段階において重要な役割を果たします。
上位の方向性を定める3C分析やSTPなどで顧客ターゲットを絞り込んだ後、どのような製品を提供し、どの価格帯で打ち出すかを検討するための基盤になるからです。流通や販促を整合する際にも役立つため、戦略全体の要といえます。
サービスマーケティングにおける7P
サービスマーケティングでは4Pに加えて、以下の3つを拡張した「7P」がよく用いられます。
- ・People(人)
- ・Process(プロセス)
- ・Physical Evidence(物的証拠)
これら3つの要素は、無形財であるサービスの提供品質を可視化し、顧客体験を向上させるために欠かせない観点です。
たとえばPeopleは、スタッフの接客態度やスキルがサービス全体の評価に直結する場合に重視されます。Processは、サービス提供の手順やオペレーションの最適化を指し、利用者がスムーズに体験できる流れを設計するうえで検討すべきポイントです。Physical Evidenceは店舗の内装・雰囲気・スタッフの制服、あるいはオンライン上であればWebサイトのデザインなど、有形要素を示す概念として活用されます。これらを加味することにより、サービス独自の強みや課題がより明確になり、改善策を具体化しやすくなるのです。
近年はオンライン接点の増加により、WebサイトやアプリのUI・UX改善が7Pの一環として語られる機会も増えています。とくにサブスクリプション型ビジネスや長期契約を求める業態では、継続利用を促す体験設計やスタッフ教育の見直しが欠かせません。こうした取り組みを積み重ねることで、競争力のあるサービスブランドを築けます。
4P分析と3C分析・4C分析の違いとは?

マーケティング分析には、4P分析のほかに3C分析や4C分析が存在します。これらはそれぞれ異なる視点から市場を捉えるフレームワークであり、適切に使い分けることで、戦略の全体像をより深く理解できるのが特徴です。以下からは、4P分析と4C分析、3C分析の違いについて簡単に解説します。
4C分析との違い
4C分析は、顧客(Customer)・コスト(Cost)・利便性(Convenience)・コミュニケーション(Communication)に焦点を当てる手法です。4P分析が企業の視点から戦略を立てるのに対し、4C分析は顧客の視点を重視し、最適化を図る点が特徴です。
たとえば価格設定についても、4Pが「自社の利益」や「原価」を基準に検討する傾向が強いのに対し、4Cは「顧客が感じる負担」や「支払い方法の利便性」を重視します。デジタルチャネルの多様化や消費者意識の変化が進む現在、4Cの考え方はブランドのファン獲得や顧客ロイヤルティの向上につながりやすいといわれています。
3C分析との違い
3C分析は、Customer(顧客)・Company(自社)・Competitor(競合)の3つの視点を軸とするフレームワークです。市場規模や顧客の嗜好、自社のリソース、競合他社の動向などを総合的に把握し、ビジネスチャンスとリスクを洗い出す段階で利用されます。
一方で4P分析は、その3C分析やSTPなどを経て明確にしたターゲットや自社優位性を踏まえ、具体的なアクションプランを形にする手段です。つまり、3C分析は戦略立案の初期段階で「現状を把握し方向性を定める」ために活用され、4P分析は「具体的な施策を設計し実行に移す」役割を担います。
4P分析の具体的な進め方

4P分析では、製品や価格の検討から流通チャネルの選定、販促方法の決定までを体系的に行います。以下のステップを意識することで、より効果的な施策立案が可能です。
- ・Product(製品)の分析
- ・Price(価格)の設定
- ・Place(流通)のチャネル選定
- ・Promotion(販促)の効果的な展開
Product(製品)の分析
最初に扱うProduct(製品)は、提供価値の核心を成す要素です。具体的には製品の品質・機能・デザイン、さらにはブランドイメージなどを多角的に検討します。
たとえば新商品をリリースする際は、市場調査を通じてユーザーが本当に求めている特長を把握することが大切です。そこで競合製品との比較を行い、自社が差別化できるポイントを明確にします。加えてサポート体制や保証内容など、購入後の体験も検討対象に含めると、顧客満足度を高めやすいといえます。
とくにITサービスやサブスクリプション型ビジネスでは、機能拡張やバージョンアップが容易なため、顧客の利用状況を踏まえながら定期的に改善を施すフローが欠かせません。こうした一連の取り組みが、製品価値を高める基礎になります。
Price(価格)の設定
Price(価格)を定める段階では、コスト計算や利益目標だけでなく、顧客が感じる妥当性も重視します。高価格帯に設定するとプレミアム感を演出できる半面、ターゲットが狭まる懸念もあるため、ブランド戦略や顧客層との適合を見極めることが欠かせません。
逆に低価格路線で大衆向けを狙う場合は、販売数量とコスト削減策をしっかりと検討しないと利益率が低下します。値引きやクーポンなどの施策も価格戦略に含まれるため、セール時期やキャンペーン期間をどの程度設定するかも考慮が必要です。とくにサブスクリプション型の料金設計では、初月無料や段階的なプラン変更などを柔軟に組み込み、長期契約へとつなげる誘導策がよく使われています。
Place(流通)のチャネル選定
Place(流通)では、製品・サービスが顧客に届くまでの経路をいかに最適化するかが焦点です。小売店への卸売なのか、自社ECサイトやマーケットプレイスを活用するのか、あるいは実店舗とオンラインの併用で相乗効果を狙うのかなど、販売チャネルの組み合わせが検討課題になります。
流通コスト・在庫管理体制・配送スピードなども加味する必要があり、顧客が望むタイミングや場所で手に取れる仕組みを作れれば、満足度の向上が期待できます。
昨今はサブスク型やD2C(Direct to Consumer)の台頭もあり、流通の再設計を行う企業が増加しています。独自のサプライチェーンを構築できれば、他社と差別化しやすくなるでしょう。
Promotion(販促)の効果的な展開
最後のPromotion(販促)は、ターゲット顧客に向けて製品・サービスの魅力を伝達する取り組み全般を指します。広告やSNS運用、イベントやPRなど多種多様な手段が存在するため、商品特性やターゲットのメディア接触状況に適合したチャネルを選ぶことが重要です。
口コミ効果を狙ったSNSキャンペーンや、インフルエンサーマーケティングを活用する事例も増えています。販売促進では、利用者が実際に試せる体験会や無料トライアルを設けることで、「本当に役立つ」と感じてもらいやすくなります。
長期的なブランド価値向上を目指すなら、一度きりの販促にとどまらず、継続的にコミュニケーションを図る方法も視野に入れると効果的です
4P分析を活用したマーケティング戦略のポイント

実際にRPAを導入する段階では、ただツールを購入するだけではうまく機能しません。いくつかの重要4P分析は、ただ要素を羅列するだけでは十分な成果を得られません。
以下に挙げる3つのポイントを意識しつつ、マーケティング戦略全体を考えることで、より実践的な活用が可能になります。
- ・ターゲットに合わせた4Pの最適化
- ・競争優位性を活かした価格戦略
- ・流通チャネルの多様化による市場拡大
- ・販促手法の組み合わせによる効果最大化
それぞれのポイントについて、順番に解説します。
ターゲットに合わせた4Pの最適化
まず、ターゲット顧客のニーズを正確に把握する必要があります。3C分析や顧客調査を通じて得た情報を踏まえ、どのような機能や価値に魅力を感じるのかを徹底的に洗い出すことが肝要です。
たとえば高級志向の顧客には品質とブランドイメージを重視し、価格よりも希少性が重要になります。
一方でコストパフォーマンスを重視する層には、価格や使い勝手が購買を決める大きな要因になることが多いです。こうした違いを4P各要素に落とし込み、無駄のない施策を組み上げることがポイントといえます。
競争優位性を活かした価格戦略
次に、競合との比較を行い、自社の強みを最大限に活かすことが欠かせません。似たような製品を提供している企業が多い場合、差別化要素を明確にしないと価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。製品開発の段階で付加価値を生み出すのか、販促によってブランドストーリーを訴求するのかなど、戦略を一貫させることが大切です。
たとえば大手と競う場合、スピード感やニッチな顧客対応など、大企業には真似しにくい部分をアピールすると優位に立ちやすくなります。
流通チャネルの多様化による市場拡大
顧客接点の強化にも注目すべきです。流通チャネルを増やすだけでなく、オンラインとオフラインを連携させたオムニチャネル戦略を展開する企業が増えています。店舗では試してもらい、オンラインでは時間や場所を選ばず購入できるようにするなど、顧客の行動パターンに合わせた利便性を高めることが重要です。
また、問い合わせ対応やカスタマーサポートを強化し、購入前後の不安を速やかに解消できれば、顧客満足度が高まりリピート率も向上します。
販促手法の組み合わせによる効果最大化
最後に、長期的なブランド価値を見据える姿勢が求められます。一時的な値下げや大量広告で売上を伸ばす手法もありますが、継続的なファンを獲得するには製品品質やアフターサポート、顧客とのコミュニケーションなどを継続的に改善しなければなりません。
とくにSNS時代は評判が拡散しやすいため、優れた顧客体験の提供が評価につながります。こうしたブランドロイヤルティの醸成こそが、4P分析を活かした戦略の核となるといえるでしょう。
4P分析・7P分析の活用事例

実際に4P分析や7P分析を導入する企業が増加しています。以下では、具体的にどのようにこれらのフレームワークを活用し成果を出したのか、事例を2つピックアップして紹介します。
4P分析の成功事例【食品・飲料業のケース】
ある飲料・食品メーカーは、特定の野菜ジュースを通じて4P分析を活用し、戦略的な差別化を図っています。本商品は通販限定で提供され、他の野菜ジュースと比べて高価格に設定されている点が特徴です。
では、4Pの各要素を見ていきましょう。
| Product(製品) | 緑黄色野菜を使用した機能性表示食品として、健康を意識する中高年層に支持される設計となっています。企業のブランドコンセプトとも一致しており、企業イメージの強化にも貢献しています。 |
| Price(価格) | 30本5,400円(2024年7月時点)と競合の野菜ジュースより高めですが、ターゲット層の平均年収を考慮すると受け入れられやすい価格設定です。さらに、定期コースの割引を設けることで継続購入を促進する仕組みを整えています。 |
| Place(流通) | あえて通販限定とすることでプレミアム感を演出し、値崩れを防いでいます。また、購入データを活用し、他の健康食品や飲料のマーケティングにも活かしています。 |
| Promotion(販促活動) | ターゲット層である中高年向けに新聞広告を活用し、効果的な訴求を行いました。 |
7P分析の成功事例【フードデリバリー業のケース】
フードデリバリー業界では、7P分析を活用することで市場競争力を高め、短期間でシェアを拡大した企業が存在します。
とくに、飲食店・ユーザー・配達パートナーの3者にとって最適な仕組みを構築し、サービスの品質向上と顧客満足度の向上を実現しています。ここでは、7Pの観点からその戦略を見ていきましょう。
| Product(製品) | 飲食店は宅配業務をアウトソーシングでき、ユーザーは外出せずに食事を楽しめます。配達パートナーにとっては、空き時間を活用した収入源となります。 |
| Price(価格) | 飲食店・ユーザー・配達パートナーの3者から手数料を徴収する仕組みです。配達パートナーの報酬は、需要や時間帯に応じて変動します。 |
| Place(流通) | 都市部を中心に展開し、配達効率を最大化しています。利用データを活用し、最適な配達エリアを設定しています。 |
| Promotion(販促活動) | オンライン広告やテレビCM、クーポン配布など、多角的な施策を実施しています。とくに、新規ユーザー向けの割引が効果的です。 |
| People(人) | ユーザー・飲食店・配達パートナーが相互に評価できるシステムを導入し、サービスの信頼性向上につなげています。 |
| Process(プロセス) | 注文から決済、配達までをアプリで完結できる仕組みを整え、キャッシュレス決済に対応しています。 |
| Physical Evidence(物的証拠) | 統一デザインの配達バッグやアプリを採用し、ブランドの認知度と信頼性を高めています。 |
このように、7P分析を活用することで、フードデリバリー業界では利便性と収益性を両立させた戦略が展開されており、継続的な市場拡大が可能となっています。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

デジタル化が進むなかで、業務効率化やコスト削減が企業の重要課題となっています。
そこで注目されるのがRPA(Robotic Process Automation)の活用です。RPA導入は、4P分析(製品・価格・流通・販促)や4C分析(顧客視点での価値提供)、3C分析(市場・競合・自社)の視点を活かすことで、より効果的になります。
たとえば、4P分析では業務改善の戦略設計、4C分析では顧客体験の向上、3C分析では競争優位性の確保につながります。そこでおすすめなのが、ブルーテック株式会社の『おじどうさん』です。プログラミング不要で簡単に使え、請求書処理やデータ転記などの自動化に優れ、ヒューマンエラーの削減や担当者の負担軽減が可能です。さらに、導入サポートも充実しており、中小企業から大手企業まで幅広く活用されています。
RPAを戦略的に導入し、業務改善を進めるなら『おじどうさん』がおすすめです。
まとめ

4P分析は、マーケティング戦略を具体化するうえで欠かせません。製品の魅力や価格設定・流通チャネル・販促方法を一貫して考えることで、顧客に届ける価値を最大化することが可能です。
また、サービス領域では7P分析を活用することで、接客・プロセス設計・ブランドの信頼性を高めるための要素も考慮でき、より包括的なプランニングも可能になります。3C分析や4C分析と組み合わせることで、市場環境や顧客のニーズを深く理解し、自社の強みを活かした最適な施策を選択できるようになります。
本記事で紹介した『おじどうさん』のようなRPAツールを活用すれば、業務の効率化とマーケティング戦略の最適化を同時に進めることも可能です。企業の競争力を高めるためにも、積極的に取り入れていきましょう。