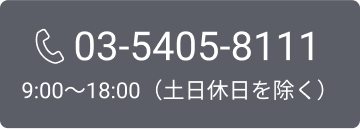中小企業にRPA導入が必要?メリットや導入事例を分かりやすく解説

近年、多くの業種で生産性向上が求められるようになりました。とくに人手不足やコスト削減のプレッシャーが大きい中小企業では、業務を自動化して省力化を図るニーズが急速に高まっています。しかし、具体的な導入手順や利点を十分に理解しきれない経営者も少なくありません。
そこで本記事では、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の基本から、導入のメリット、さらには具体的な活用事例までを詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
【この記事の内容】
そもそもRPAとは?
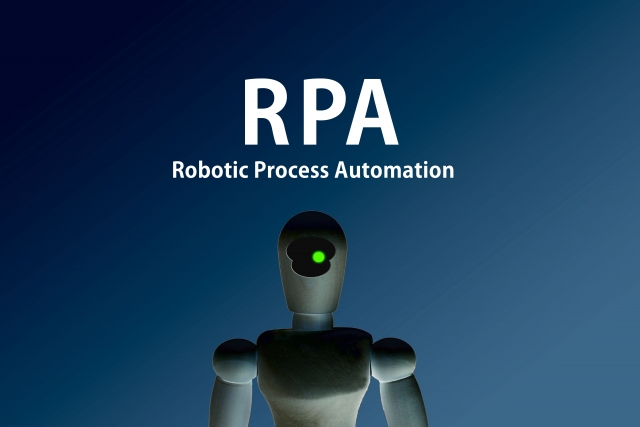
RPA(Robotic Process Automation)とは、ソフトウェアのロボットを使って定型的な事務作業などを自動化する仕組みを指します。一連の操作を記録し、仮想的なオペレーターが人間に代わって実行するため、ヒューマンエラーを防ぎながら処理を素早く行えます。
しかし、AIと完全に同じものではありません。あくまでもルールベースの自動化を主眼に置き、決められた手順や判断基準を忠実に再現する点に特色があります。最近ではAI技術との連携も進み、より高度な業務へ適用するケースが増えてきました。アメリカやヨーロッパの大手企業だけでなく、日本国内においても2023年時点で導入が活発化してきたといわれる状況です。
さらにクラウド型のRPAツールが登場し、環境構築の手間を大幅に削減できる点も注目されるようになりました。これらの要素を踏まえ、中小企業でも活用できる技術として期待が高まる現状だといえます。
中小企業でRPA導入が必要な理由

コスト削減や生産性向上の観点から、中小企業にとってRPA導入は大きな戦略的意義があります。
以下では、中小企業がRPAを導入すべき具体的な理由を3つ紹介します。
- ・コスト競争力の強化と資源の最適配分
- ・限られた人員での業務効率最大化
- ・変化する市場への迅速な対応
限られた人員での業務効率最大化
第一に、限られた人員であっても高い生産性を維持する必要がある点が挙げられます。大企業と比べ、中小企業は人件費や雇用にかかるリソースに大きな制約が生じやすいです。RPAを導入すると、繰り返し作業の自動化によって担当者の負担が軽減されます。
たとえば請求書や契約書のデータ入力をロボットに任せることで、ミスが減るだけでなく作業時間も短縮しやすくなるでしょう。これによって余力が生まれ、新規顧客開拓や品質向上など、より高度な分野へマンパワーを振り分けられるようになります。
変化する市場への迅速な対応
第二に、市場の変化に素早く対応するためにもRPAが必要といえます。消費者のニーズは日々変化し、それに追随しながら新商品や新サービスの開発にリソースを回さなければなりません。
紙ベースの手続きやメール対応などに追われていると、変化の波に遅れを取る懸念があります。RPAを導入すると、定型的なカスタマーサポートや社内承認フローの一部を自動化できます。これにより、スタッフが市場調査や戦略立案といったクリエイティブなタスクへ集中しやすくなる点が大きなメリットです。
コスト競争力の強化と資源の最適配分
第三に、コスト競争力を高められる可能性がある点が大きいです。RPAは導入コストが高いイメージがありますが、近年はクラウド型や月額利用プランなど、比較的手軽に始められるサービスも増えています。
実際に、請求処理や在庫管理などの業務をロボットへ一任することで、残業代やアウトソーシング費用が大幅に圧縮される事例も報告されています。結果的に人材育成へ資金を回せるようになり、中長期的な目線で競合他社と差別化を図りやすくなるでしょう。
中小企業におけるRPA導入の傾向と推移

近年、国内外を問わず中小企業においてRPAを導入する動きが徐々に加速していると報じられています。株式会社MM総研の「RPA国内利用動向調査2020」によると、2018年6月時点でRPAを導入済みの中堅・中小企業は17%でしたが、2019年11月には25%まで増加しました。
また、導入を検討中の企業も33%から44%へと拡大しており、多くの企業が今まさにRPAの活用を視野に入れていることが分かります。
とくに2021年以降は、クラウドサービスの普及やツールの低コスト化が追い風となり、導入のハードルが下がる傾向が際立っています。さらに、日本情報処理開発協会などが公表するデータによれば、小規模事業者向けのRPA支援サービスが年々増加しており、自動化できる業務範囲が広がっている点も見逃せません。
この流れを受け、今後は単純作業の自動化にとどまらず、より専門性の高いタスクへの適用を目指す企業も増える見通しです。中小企業においても、競争力を維持・向上させるためには、RPAの導入を積極的に検討することが重要となるでしょう。
中小企業でRPA導入が進んでいない背景

急速に注目されているRPAですが、すべての中小企業で導入が一様に進んでいるわけではありません。
なぜ導入を躊躇するのか、中小企業でRPA導入が進まない背景を3つ紹介します。
- ・導入コストへの懸念と投資の優先度
- ・ITリテラシーの不足と現場の不安
- ・導入効果の見えにくさと意思決定の遅れ
導入コストへの懸念と投資の優先度
まず、導入コストに対する懸念が挙げられます。中小企業の場合、限られた予算の中で生産設備や人材教育など、先行投資を要する項目が多数あるはずです。RPA導入そのものが安価になりつつあるとはいえ、選定からシステム設計、運用開始後のサポートまで含めると、一定の費用は発生します。
とくに初期導入時に社内のIT部門が不十分な場合、外部のコンサルタントを頼らざるを得ず、想定よりも出費が増えるケースが散見されます。こうしたコスト面の不安が、導入が先送りになる要因となるようです。
ITリテラシーの不足と現場の不安
次に、従業員のITリテラシーが追いついていない点も無視できない要因です。RPAツールは操作性が向上しているとはいえ、設定変更や業務フローの見直しには基本的なIT知識が必要とされます。
社内に専門人材がおらず、外注ばかりに頼ると、ツールのアップデートやメンテナンスを適切に行いにくくなる恐れがあります。また、従業員が「自分の業務が奪われるのでは」といった不安を抱いてしまう場合もあるでしょう。
このように人的リソースの問題から、RPA導入が進みにくいケースもあるのです。
導入効果の見えにくさと意思決定の遅れ
さらに、具体的な導入効果が見えにくいという課題も指摘されています。RPAによる自動化が、どのくらいコスト削減や業務効率化に貢献するのかを事前に数値化できないと、経営者は投資をためらう傾向があります。
試験導入の段階で目立った成果を測定しにくい場合、本格運用に踏み切る判断が下せないのです。
とくに中小企業では、リスクを最小化しながら事業を継続する必要があります。そのため、定量的な効果検証が難しい段階で二の足を踏んでしまい、導入自体が停滞してしまうことが多くなります。
中小企業にRPAを導入するメリット

導入をためらう要素はあるものの、RPAがもたらすメリットは非常に大きいです。
ここでは代表的な3つの利点を示し、中小企業が得られる具体的な効果を簡潔に解説します。
- ・業務の自動化による大幅な時間短縮
- ・ヒューマンエラーの削減と業務の正確性向上
- ・業務プロセスの可視化と最適化
業務の自動化による大幅な時間短縮
中小企業にRPAを導入する最大のメリットのひとつが、業務時間を大幅に短縮できる点です。RPAを活用すれば、請求書処理や在庫データ管理などの定型業務を、高速かつ正確に処理できます。
人間が作業をする場合はヒューマンエラーが発生するリスクがありますが、RPAならルールに従って一貫した処理を実行できるため、ミスを防ぎながら業務のスピードを向上させることが可能です。その結果、従業員はより重要な業務に時間を割けるようになり、全体の生産性向上にもつながるでしょう。
ヒューマンエラーの削減と業務の正確性向上
中小企業にRPAを導入することで得られるメリットのひとつが、ヒューマンエラーの大幅な削減です。
データ入力や書類処理などの反復作業は、人が行う以上、入力ミスや確認漏れが発生しやすくなります。しかし、RPAなら同じ手続きを正確に繰り返すため、入力ミスや数値の誤りを最小限に抑えることが可能です。
とくに、監査対応の厳格化が進む現在では、業務の正確性を確保することが信頼性向上にも直結します。RPAの活用により、より安心できる業務環境を構築できるでしょう。
業務プロセスの可視化と最適化
RPAを導入することで、業務プロセスの可視化と改善が進むのも大きなメリットです。
業務プロセスを可視化するには、既存のフローを洗い出す必要があります。洗い出すことにより結果的に無駄なステップや重複作業が発見されるため、業務プロセス全体の見直しが進むでしょう。最適化したうえでロボットに任せる流れが生まれると、組織全体のパフォーマンスが上がり、将来的な拡張もしやすくなります。
中小企業にRPAを導入する際のポイント

実際にRPAを導入する段階では、ただツールを購入するだけではうまく機能しません。いくつかの重要な視点を押さえておく必要があります。以下では3つのポイントを提示します。
- ・運用体制の整備と継続的な管理
- ・導入目標の明確化と段階的な展開
- ・ツール選定時のITスキル考慮と事前検証
導入目標の明確化と段階的な展開
導入目標を明確に設定することが最初のポイントです。どの業務をどの程度自動化し、どんな成果を得たいかを具体的に定めないと、効果測定ができずに終わります。たとえば「毎月の請求処理に費やす時間を50%削減する」など、数値目標を掲げると進捗管理が容易です。
また、短期間で結果を出したいあまり、手当たり次第に自動化するのは危険といえます。優先度の高い業務からテスト導入を行い、少しずつ範囲を拡大するほうが失敗リスクを抑えられます。
ツール選定時のITスキル考慮と事前検証
ツール選定時には、社内のITスキルレベルを考慮する必要があります。専門知識が少ない現場でも扱いやすいUIを備えたRPAを選ぶと、研修や運用サポートの負担が軽くなるでしょう。
最近のクラウド型RPAには、プログラミング不要でシナリオ作成できる製品も登場しています。さらに、導入前に無料トライアルを実施し、実際の業務データを用いて動作確認を行うことも有効です。使いこなせるかどうかを事前に見極めると、導入後の混乱を最小限にできます。
運用体制の整備と継続的な管理
事前検証で有用性を確認できたら、本格導入の段階へ移行します。まずは対象業務の範囲を広げ、シナリオを拡充していきます。ロボット開発時には、現場担当者やIT部門の連携が不可欠です。動作確認を密に行い、運用開始後に想定外のトラブルが起きないよう準備を整えましょう。並行して、社内へのトレーニングや運用マニュアルの作成にも注力するとスムーズに定着します。
導入後は定期的に効果測定を行い、業務フローの変化に応じたシナリオ修正を実施して最適化を継続することが重要です。
中小企業にRPAを導入する際の注意点

導入メリットは大きい一方、進め方を誤るとコストやトラブルが膨れ上がるリスクもあります。
ここでは5つの注意点を挙げ、それぞれの対策や見落としを防ぐヒントを共有します。
- ・ROI(投資対効果)の適切な試算と評価
- ・適用業務の慎重な選定
- ・データセキュリティの強化
- ・外部ベンダーとの契約内容の明確化
- ・社内浸透のための教育とコミュニケーション
ROI(投資対効果)の適切な試算と評価
RPAを導入する前に、ROI(投資対効果)をしっかりと試算する必要があります。具体的にどれだけ工数や人件費を削減できるのか、明確な指標を定めずに導入すると、後々「期待ほど費用対効果が出ない」といった不満が噴出しがちです。
たとえば、導入コストに対して何年で回収できるのか、どの業務でどれだけの時間短縮が見込めるのかを定量的に分析することが重要です。導入後も定期的に実績を評価しながらPDCAサイクルを回すことで、投資判断のズレを防ぎ、RPAの効果を最大限に引き出しましょう。
適用業務の慎重な選定
まずは請求書の処理や在庫確認など、フローが明確で繰り返し頻度が高いタスクから着手するのが堅実です。
小規模な業務から導入し、運用しながら課題を洗い出すことで、安定した運用体制を構築できます。
効果を検証しながら、より複雑な業務へと段階的に適用範囲を広げていくことで、リスクを抑えつつRPAの活用を最大化できるでしょう。
データセキュリティの強化
データの取り扱いには細心の注意を払う必要があります。RPAで扱う情報には顧客名簿や取引情報など機密性の高いデータが含まれる場合が多いです。
セキュリティ対策を怠ると不正アクセスや情報漏えいのリスクが高まります。アクセス制限や暗号化の仕組みを導入し、定期的に監査する体制を整備してください。
外部ベンダーとの契約内容の明確化
RPAベンダーや外部コンサルとの連携ルールを事前に明確にしておくことが重要です。契約内容を十分に確認せずに導入すると、追加費用の発生や想定外のコスト増につながるリスクがあります。そのため、サポート範囲・保守内容・アップデートの頻度・契約更新の条件などを事前に把握し、導入後のトラブルを未然に防ぐことが必要です。
とくに、料金体系やサポート体制を細かくチェックし、不明点は導入前にしっかり交渉することが重要です。導入段階での交渉がその後の成果を大きく左右するため、将来的な運用コストやトラブル対応の負担を最小限に抑えられるよう、慎重に進めましょう。
社内浸透のための教育とコミュニケーション
社内浸透を図るための教育とコミュニケーションも欠かせません。RPA導入によって「自分の仕事がなくなるのでは」と心配する従業員が出る可能性もあります。
そのため、RPAで自動化される部分と、人間の創造的な役割がどう変化するのかを明示しておく必要があります。早期に理解を得れば、スムーズな定着が期待できるでしょう。
中小企業のRPA活用事例

実際にRPAを導入する中小企業は年々増加しており、成果を上げている事例が多数報告されています。ここでは、実際の導入事例を3つ紹介します。これらの事例を参考に、自社での活用方法をイメージしてみてください。
サービス業:交通費精算チェック業務の自動化
ある企業では、従業員から提出される交通費精算書の金額チェックに多くの工数がかかっていました。RPAを導入し、交通費精算の申請内容をウェブ上の情報と照合し、最適なルートの金額かどうかを判定するプロセスを自動化。これにより、毎月の締め日に半日かかっていた約80人分のチェック作業と修正依頼のメール送信が不要となり、ほかの業務に時間を充てることが可能になりました。
さらに、目視でのチェックが自動化されたことで、ヒューマンエラーの回避にもつながりました。
製造業:日次売上の集計報告業務の自動化
サービス業の予約管理システムにRPAを導入した事例も注目に値します。複数の予約サイトやメールから情報を取得し、顧客データを社内システムに手入力していた工程を自動化したケースです。
これによって、予約状況の一元化とダブルブッキング防止がスムーズに行われ、顧客満足度も向上したといいます。従来は人為的ミスでトラブルが起きやすかった部分をロボットが正確に処理するため、スタッフが追加サービスの企画や接客品質の向上に時間を回せるようになりました。
金融業界:投資信託口座開設業務の自動化
ある銀行では、投資信託の口座開設業務にRPAを導入しました。従来、口座開設申込書のスキャン・顧客情報の確認・修正・システムへのデータ入力など、多くの手作業が必要でした。
RPAとOCR(光学文字認識)を組み合わせることで、申込書のデータ抽出からシステムへの入力までを自動化し、業務時間を従来の3分の1に短縮することに成功。これにより、人的ミスの削減や業務効率の大幅な向上が実現しました。
この事例から、RPAの導入により、金融業界における複雑な手続きや大量のデータ処理が効率化され、業務の正確性とスピードが向上することが分かります。
失敗しないRPAツールの選び方
RPAを成功させるためには、企業の規模や要件に合ったツールを選ぶことが肝心です。
ここでは、導入時に重視したい5つのポイントを取り上げ、それぞれの見極め方を解説します。
- ・業務範囲との相性を確認する
- ・操作性とユーザビリティの確認
- ・セキュリティ機能の充実度を確認する
- ・コストパフォーマンスの比較
- ・サポート体制とコミュニティの活用
業務範囲との相性を確認する
RPAの導入に失敗しないためには、自社の業務範囲との相性を確認する点が重要です。RPAによって自動化したいタスクは何か、手動作業のボトルネックはどこにあるかを明確にしてからツールを比較しましょう。
複数システムと連携が必要な場合は、対応しているAPIや拡張機能の有無も要確認です。ここの判断を誤ると、後戻りの手間が大きくなるので注意しましょう。
操作性とユーザビリティの確認
RPAを導入する際に「操作のしやすさ」は見逃せないポイントです。現場担当者がノーコードやローコードでシナリオを作成できるRPA製品は、導入後の改修コストを抑える助けになります。
プログラミングが苦手な人でも扱えるUIかどうか、サポート体制は十分か、こうした点を試用版などで確かめておくと安全です。導入後の教育負担にも直結するため「直感的に操作できるか」「業務フローに適した設計か」などを事前に確認し、スムーズな定着を図りましょう。
セキュリティ機能の充実度を確認する
RPAの導入に失敗しないためにも、セキュリティ機能の充実度を必ずチェックしてください。顧客情報や決算データなど、取り扱う情報が機密性を要する場合は、暗号化やアクセス制御の仕組みが整っているツールを選ぶことが望ましいです。
運用時の監査ログ取得や不正アクセス検知など、セキュリティオプションを拡充できる製品も増えています。企業の信頼を守るためにも、データ保護対策やアクセス管理の厳格化は軽視できない重要なポイントです。
コストパフォーマンスの比較
コストパフォーマンスを比較することも不可欠です。月額制や年間ライセンス制、機能追加ごとの追加料金など、RPAの料金体系は多様化しています。
自社の使用量や拡張性を踏まえて、最終的にどの程度のコストが発生するのかを試算しておきましょう。安価に見えても、オプションが必要になるとトータルで割高になるケースもあるため要注意です。
サポート体制とコミュニティの活用
最後に、ベンダーやコミュニティのサポート力も見極めたいです。導入直後はもちろん、日々の運用で疑問やトラブルが発生したときに、迅速な問い合わせ対応が得られるかどうかは大きな安心材料となります。
また、ユーザーコミュニティが活発なら、導入事例やノウハウが豊富に共有される点もメリットです。
長期的な視点で評価し、安心して運用を続けられるツールを選びましょう。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

中小企業がRPAを導入する際、国産サービスでサポート体制が整ったツールを選ぶのは有力な手段です。なかでもブルーテック株式会社が提供する『おじどうさん』は、専任のサポート窓口を設けており、初心者でも扱いやすいインターフェースが評価されています。
さらに、AIモジュールとの連携機能を追加で利用できるため、単純作業に留まらず幅広い業務へ適用しやすい点が特徴です。無料のトライアルプランも用意されているので、実際の業務で検証してから導入可否を決定しやすくなるでしょう。
RPAの導入を考えているなら、手厚いサポートが魅力の『おじどうさん』をぜひ検討してみてください。
まとめ

本記事では、中小企業におけるRPA導入の理由やメリット、具体的な事例を中心に解説しました。導入コストやIT人材の不足といったハードルは存在しますが、適切なツール選定や段階的な運用を心掛ければ、高い投資対効果を得られる可能性があります。
生産性向上と従業員の負荷軽減を両立する手段として、RPAは今後ますます注目度を増していくでしょう。RPAの導入を検討する際は、ここで紹介したポイントや注意点を再確認し、目的に合ったソリューションを選んでください。